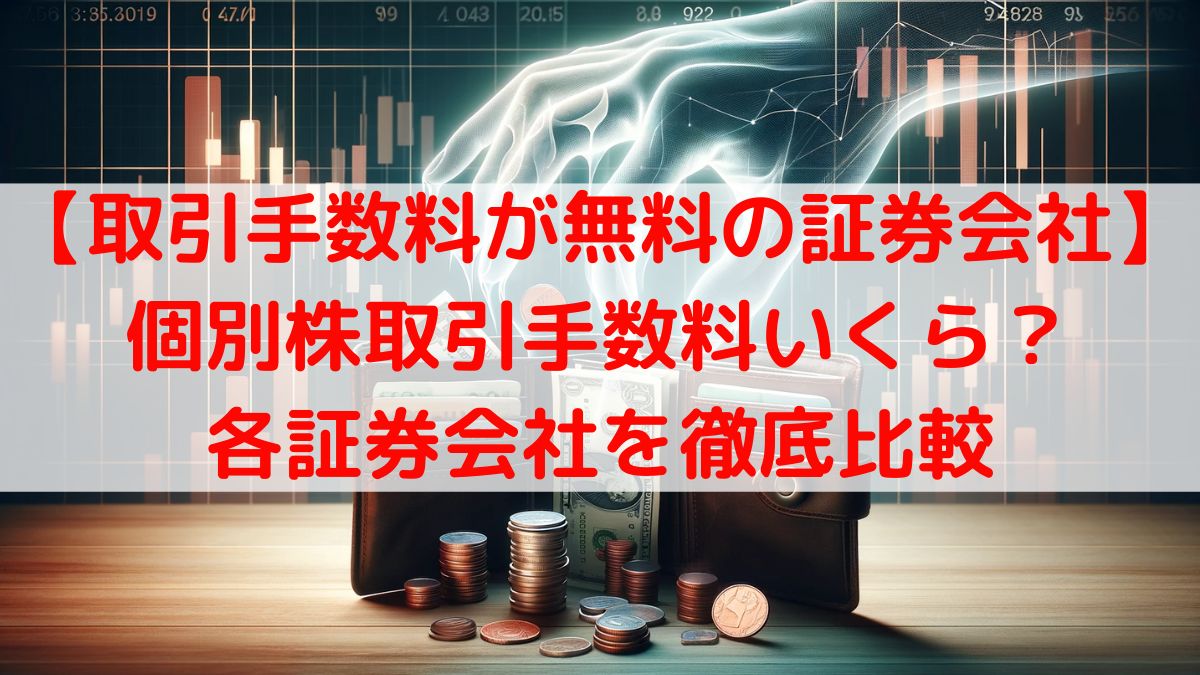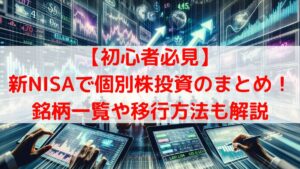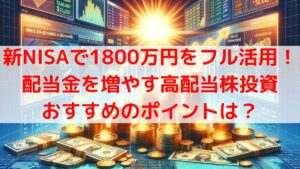2024年1月よりスタートする新NISA制度は利益に対して非課税となるため、多くの投資家にとって魅力的な制度となっています。しかし、個別株投資によって生じる取引手数料はコストとなるため、利益に影響を与えます。
今回は新NISAの個別株取引手数料の仕組みや料金体系、また手数料削減の方法について詳細に解説します。さらに、取引手数料が無料になる証券会社とサービスの比較内容もご紹介します。
この記事を読むことで、新NISAの個別株投資で発生する取引手数料の仕組みを学ぶことができます。さらに、取引手数料の安い証券会社を選んで長期的なコスト削減を実現し、資産運用の効率を高めることができるようになります。
新NISAとは?初心者にも分かりやすい解説
新NISA制度は、税制優遇を受けられる日本の個人投資促進プログラムです。
この制度は投資で得た利益が非課税になったり、年間投資枠が拡大されるなどのメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。
そこで、新NISAの基本についてや、メリットとデメリットについて解説します。
新NISAの基本知識
新NISAは、日本の個人向け投資促進のための税制優遇制度です。この制度では、投資によって得られた利益に対して税金はかかりません。
新NISAは、旧NISA制度の後継として、より長期的な資産形成を目指す人々に向けて設計されています。
また、成長投資枠とつみたて投資枠の2種類があります。成長投資枠の年間投資枠は240万円、つみたて投資枠の年間投資枠は120万円となります。
そして、この2つの投資枠を合わせた、非課税保有限度額は最大1800万円となります。例えば、成長投資枠とつみたて投資枠を併用して年間100万円を投資した場合、18年で非課税保有限度額の上限に達します。その間、投資で得た利益は非課税扱いとなります。
新NISAのメリットとデメリット
新NISAのメリットは、非課税期間が無期限であるため、長期間にわたって安心して投資を続けることができる点です。また、年間投資枠が拡大したため、より大きな資産形成が期待できます。
しかし、デメリットも存在します。新NISAの投資対象商品は限定されており、リスキーな商品には投資できません。これは、よりリスクの高い商品に投資して大きなリターンを目指したい投資家にとっては不利となります。
また、新NISAには年間投資枠の制限があるため、長期間にわたる計画的な資金配分が必要となります。
例えば、つみたて投資枠を活用する場合、毎月一定額をコツコツと投資することが推奨されます。そのため、市場の急激な上昇局面でチャンスが到来したときでも、年間投資枠が制限されているため、一度に大金を投入することができない場合があります。
新NISAは長期的な資産形成を目指す個人投資家にとって有効な制度であるため、自分の投資スタイルに合わせて利用することが重要です。
新NISAの個別株投資入門

個別株投資はハイリスク・ハイリターンになるため、市場の動向を理解して分散投資を行うことが大切です。
また個別株投資を行う場合は、新NISAの口座を開設する必要があります。
そこで、個別株投資の基本と投資までの流れについて解説します。
個別株投資の基本
個別株投資は、企業の株式を購入し、その企業の成長とともに投資のリターンを得る方法です。個別株投資の魅力は、株価の上昇や配当金によってリターンを得ることができる点です。
しかし、市場の変動や企業業績の不振により、損失を被るリスクも存在します。
ここでは、個別株投資の基本的なポイントを紹介します。
ハイリスク・ハイリターン
個別株投資では高いリターンが期待できる一方で、リスクも高くなります。例えば、企業の業績が悪化した場合、株価が下がる可能性があります。
市場動向の理解
株価は市場の供給と需要によって決まるため、経済情報や業界ニュースを常にチェックすることが重要です。
分散投資を行う
分散投資によって、異なる業界や複数の企業に投資を行い、リスクを分散させることが大切です。
個別株投資はハイリスク・ハイリターンの投資方法となるため、1つの銘柄に集中せず、異なる業界や複数の企業に分散投資させることが大切です。
また、常に経済情報や業界ニュースをチェックして、リスクに対処するようにしましょう。
新NISAでの個別株投資の流れ
新NISAでの個別株投資は、一般的な株式投資と同じですが、利益に対して非課税になるという利点があります。
個別株投資の流れは、次の通りです。
手順1.新NISAの口座開設
まず、証券会社にて新NISAの口座を開設します。
↓
手順2.投資対象の選定
市場調査を行い、投資したい個別株を決定します。
↓
手順3.購入
新NISA口座を通じて、個別株を購入します。年間投資枠内であれば、利益は非課税となります。
↓
手順4.管理と監視
購入後は市場の動向に注意を払い、ポートフォリオを評価します。
↓
手順5.利益の確定
利益が発生した場合、売却して利益を確定します。
個別株投資を行う場合、まず証券会社で新NISAの口座を開設する必要があります。口座開設後は、個別株の売買が行えます。
そして取引手数料は、手順3で個別株を購入したときと、手順5で個別株を売却したときに発生します。
初心者必見!新NISAの個別株取引手数料の完全ガイド
新NISAの取引手数料は、コストとなって利益に影響を与えます。
取引手数料のタイプには固定手数料と変動手数料があり、取引スタイルに応じて最適な証券会社を選択することが重要です。
また手数料を削減して、コストを抑えることも大切になります。
取引手数料とは?基本を押さえる
取引手数料は、株式を売買する際に証券会社が徴収する費用です。
この手数料は、投資の際にコストとなるため、利益を左右する重要な要素となります。
取引手数料は、次の2種類に分類されます。
固定手数料
取引金額に関係なく一定額の手数料がかかる方式。
変動手数料
取引金額に応じて手数料が変動する方式。
固定手数料を採用する証券会社と、変動手数料を採用する証券会社のどちらを選ぶべきかは、投資家の取引スタイルによって変わります。
例えば、A社では1回の取引につき500円の固定手数料がかかり、B社では取引金額の0.1%が手数料としてかかるとします。
10万円分の個別株を取引した場合と、100万円分の個別株を取引きしたときにかかる取引手数料は次の通りです。
| A社(500円の固定手数料) | B社(取引金額の0.1%の手数料) | |
|---|---|---|
| 10万円の個別株を取引 | 500円 | 100円 |
| 100万円の個別株を取引 | 500円 | 1000円 |
もし10万円分の個別株を取引した場合、固定手数料を採用するA社は500円の手数料がかかり、変動手数料を採用するB社は100円の手数料しかかかりません。しかし、100万円分の個別株を取引する場合、A社は500円の手数料がかかりますが、B社は1000円の手数料がかかることになります。
つまり、少ない金額を取引する場合は、変動手数料を採用する証券会社の方が手数料負担は少なくなります。一方、大きな金額を取引する場合は、固定手数料を採用する証券会社の方が手数料負担は少なくなります。
投資家は、自分の取引スタイルに合った証券会社を選ぶことが重要です。
取引回数ごとの手数料削減テクニック
取引回数が多くなると、手数料の総額が大きくなりがちです。そこで、取引手数料を少なくするテクニックについていくつかご紹介します。
一括売買
固定手数料を採用する証券会社を利用している場合、複数の銘柄を同時に売買することで、取引手数料の金額を減らすことができます。
証券会社のキャンペーン利用
証券会社によっては、特定の期間中に手数料が無料になるキャンペーンを実施するところがあります。その期間中に取引を行えば、手数料を抑えることができます。
取引回数に応じた割引制度
一定期間内の取引回数が多い場合、手数料が割引されるプランを提供する証券会社もあります。
例えば、月に10回取引をして1回あたり500円の手数料がかかる場合、取引手数料の合計は5000円になります。もし手数料無料キャンペーン期間中にまとめて取引を行えば、5000円かかっていた手数料がタダになります。
取引手数料は、個別株投資のコストとして利益に影響を与えます。
投資家は自身の取引スタイルと頻度に合わせて、最適な証券会社を選択しましょう。
取引手数料が無料!新NISAのおすすめ証券会社を紹介

新NISAで個別株投資をするとき、できれば取引手数料が安い証券会社を選びたいものです。
けど実は、取引手数料が無料の証券会社が存在し、各社とも異なったサービスを展開しています。
そこで、取引手数料が無料の証券会社をご紹介します。
取引手数料が無料の証券会社はこの5社!
新NISAの個別株投資では、取引手数料のコストが利益に影響を与えます。そのため、少しでも手数料が安い証券会社を選びたいところです。
そんな悩みを持つ投資家のために、取引手数料が無料の証券会社をご紹介します。
| 証券会社 | 国内株及び米国株の取引手数料 | PRポイント |
|---|---|---|
| SBI証券 | 無料 | 取扱銘柄No.1、IPO銘柄の取り扱い数No.1 |
| 楽天証券 | 無料 | 楽天ポイントが貯まる、楽天銀行との連携が便利 |
| 松井証券 | 無料 | 1株から取引できる、取引ツールがシンプルで使いやすい |
| マネックス証券 | 無料 | 投資信託の取り扱い数No.1 |
| auカブコム証券 | 無料 | 取扱銘柄No.2、IPO銘柄の取り扱い数No.2 |
国内株と米国株の取引手数料は、5社とも無料となっています。
そのため、各証券会社のPRポイントを比較して、自分に合った証券会社を選ぶことが重要になります。
SBI証券:取扱銘柄数とIPO銘柄の取り扱い数No.1
SBI証券は、取扱銘柄数とIPO銘柄の取り扱い数でNo.1の証券会社です。取扱銘柄数が多いため、自分の投資したい銘柄を見つけやすいのがメリットとなります。
また、IPO銘柄の取り扱い数が多いため、IPOで大きく利益を上げたい投資家に適した証券会社となっています。
楽天証券:楽天ポイントが貯まる
楽天証券は、楽天ポイントが貯まるというメリットがあります。楽天ポイントは、楽天市場や楽天Payなどで利用できるため、日常生活で使えて便利です。
また、楽天銀行との連携が便利で、楽天銀行から楽天証券に資金を移動するときに手間がかかりません。
松井証券:1株から取引できる
松井証券は、1株から取引できるというメリットがあります。少額から投資を始めたい方や、特定の銘柄を少量だけ購入したい方におすすめです。
また、取引ツールがシンプルで使いやすいため、初心者でも安心して使えます。
マネックス証券:投資信託の取り扱い数でNo.1
マネックス証券は、投資信託の取り扱い数No.1で、豊富なラインナップの中から自分に合った投資信託を選ぶことができます。
auカブコム証券:取扱銘柄数とIPO銘柄の取り扱い数No.2
auカブコム証券は、取扱銘柄数とIPO銘柄の取り扱い数でNo.2の証券会社です。SBI証券と比べると取扱銘柄数は少ないですが、それでも十分な数の銘柄を取り扱っています。
また、IPO銘柄の取り扱い数も多いため、IPOで大きく利益を上げたい投資家に適しています。
新NISAの口座開設から取引開始まで

新NISAの口座開設は、証券会社の選定から始まり、オンラインでの申し込み、必要書類の提出を経て完了します。
また口座開設後の取引には、資金の入金から注文、取引の実行といったステップが必要です。
そこで、新NISAの口座開設から取引開始までの手順についてご紹介します。
口座開設の手順
新NISAの口座開設は、証券会社の選定から始まります。口座開設までのステップは、次の通りです。
手順1. 証券会社の選定
各証券会社の取引手数料、取引ツール、サポートサービスなどを比較検討し、自分の投資スタイルに合った証券会社を選びましょう。
↓
手順2. オンラインで申込み
選んだ証券会社のウェブサイトからオンラインで申し込みます。
↓
手順3. 必要書類の提出
本人確認書類などの提出が求められます。必要書類には、運転免許証やマイナンバーカードなどがあります。
必要書類の提出は、オンラインまたは郵送で行うことができます。
↓
手順4. 口座開設完了
提出した書類に問題がなければ、口座が開設されます。そして、取引を行うためのログイン情報などが通知されます。
新NISAの口座を開設する場合、ウェブサイトから簡単に手続きすることができます。手続き完了後、数日位で口座が開設されます。
初回入金と注文方法の基本
新NISAの口座開設が完了したら、次は資金を入金します。口座に資金が入金されると、いよいよ取引を始めることができます。
入金から取引実行までのステップは、次の通りです。
手順1. 新NISAの口座に入金
取引に必要な金額を新NISA口座に入金します。入金する金額は、投資計画に基づいて決めると良いでしょう。
↓
手順2. 注文方法の選定
個別株の購入方法には、成行注文や指値注文などがあります。
成行注文は現在の市場価格で注文を行い、指値注文は指定した価格で注文を行います。
↓
手順3. 取引の実行
投資したい個別株を選び、株数や注文方法と金額を選定します。約定すると売買が成立し、取引は終了となります。
以上が取引実行までのステップとなります。
自分に合った証券会社を選び、投資計画に基づいて取引を行いましょう。
新NISAにおける個別株投資の取引手数料についてよくある質問

最後に、新NISAにおける個別株投資の取引手数料についてよくある質問をまとめました。
Q.新NISAで個別株を購入する際の取引手数料はどのように計算されますか?
新NISAで個別株を購入する際の取引手数料は、証券会社によって異なります。一般的には、取引金額の一定割合(例えば0.1%~0.5%程度)で計算されることが多いです。
また、最低手数料が設定されている場合もあります。取引手数料は取引ごとに発生するため、頻繁に取引するとコストが高くなる可能性があります。
Q.新NISA口座での取引手数料は非課税ですか?
新NISA口座での取引手数料自体は、非課税ではありません。手数料は投資家の負担となります。
ただし、新NISA口座内で得た利益(売却益や配当金など)に関しては、非課税となります。
Q.取引手数料を抑えるための投資戦略はありますか?
取引手数料を抑えるためには、取引の回数を減らす、手数料の安い証券会社を選ぶ、長期投資を行うなどの戦略が有効です。また、手数料無料のキャンペーンを行っている証券会社を利用することも一つの方法です。
おすすめの方法は、取引手数料が無料の証券会社を利用することです。例えば、SBI証券や楽天証券などを利用した場合、取引手数料が無料となります。
新NISAの個別株取引手数料についてのまとめ
新NISAの個別株取引手数料には、固定手数料と変動手数料の2種類があります。
SBI証券や楽天証券などでは、個別株の取引手数料は無料となっています。
取引手数料は投資家にとってコストとなり、利益を左右する重要な要素です。取引手数料を抑えて利益を残すことが重要になります。