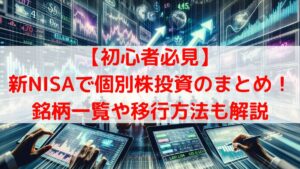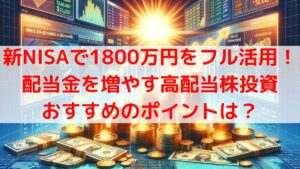2024年1月に新NISA制度がスタートし、多くの投資家が注目しています。特に、配当金に対する非課税の扱いは、旧NISA制度と比較してどのように変わったのか、そのメリットとは何か、そしてどのような条件で非課税の恩恵を受けられるのかが重要なポイントです。
今回は、新NISAと旧NISAの配当金に対する非課税の扱いの違いから、配当金が非課税になるメリット、対象となる投資商品、さらには配当金が非課税となる条件について詳しく解説します。また、高配当株の選び方からおすすめの銘柄まで、具体的な投資戦略についても紹介していきます。
この記事を読むことで、配当金を非課税で得る方法や、そのメリットを最大限に活用する方法について学ぶことができますので、最後までご覧ください。
新NISAと旧NISAの配当金に対する非課税の扱いについて

新NISAと旧NISAにおける配当金の扱いについて、大幅な改正が施されました。この制度改正は、投資家にとってどのようなメリットがあるのでしょうか?
そこで、新NISAと旧NISAの制度改正が配当金の扱いについてどのように変わったのか、解説していきます。
旧NISAの配当金の非課税扱いについて
旧NISAの場合、個別株から得られる配当金は非課税扱いでした。ただし、このメリットは非課税期間による制限があります。
具体的には、一般NISAで5年間の非課税期間があります。この非課税期間が終了すると、配当金に対して、通常の税率が適用されます。
新NISAの配当金の非課税扱いについて
新NISAが誕生し、この配当金の非課税扱いは大幅に改正されました。まず、非課税期間が無期限になったことです。そのため、永続的に非課税で配当金を受け取ることができます。
さらに、年間投資枠が拡大されました。これにより、より多くの投資から配当金を非課税で受けられる機会が増えました。
非課税期間の無期限化や年間投資枠の拡大など、新NISAは長期的な資産形成を考えている人にとって、非常に有利な制度です。
新NISAで配当金が非課税になるメリット
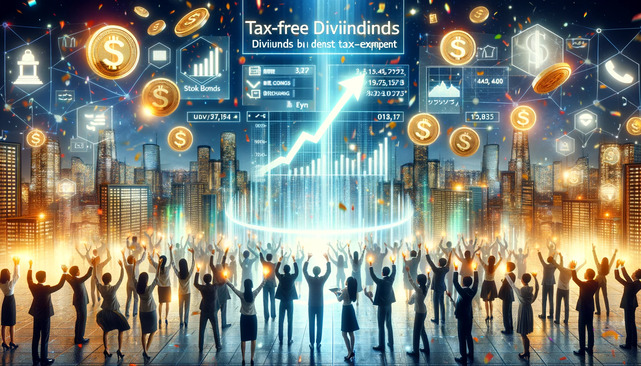
通常の課税口座で個別株投資を行った場合、配当金には約20%の税金が発生します。ところが、新NISAを利用した場合、配当金は非課税扱いとなり、税金が全額手元に残ります。
そこで、配当金が非課税になることで投資家にとってどのようなメリットがあるのか詳しく解説します。
税金負担が軽減される
通常、個別株投資で得た配当金には、約20%の税金が発生します。しかし、新NISA制度を利用することで、配当金にかかる税金の負担がなくなり、手元に残る金額が増えます。
例えば、通常の課税口座で10万円の配当金を受け取った場合、約2万円の税金が発生して、手元に残るのは8万円です。しかし、新NISA口座で10万円の配当金を受け取った場合、税金の支払いはないので、手元に残るのは10万円になります。
新NISAを利用することで配当金が非課税扱いとなり、より多くの利益を自分の資産として残すことができます。そのため、長期投資を考えている人にとって大きなメリットとなります。
資産形成が加速する
新NISAでは配当金に対して非課税扱いとなるため、受け取った配当金をそのまま再投資に回すことができます。これにより、複利の力を利用して、資産がより大きくなっていきます。
例えば、通常の課税口座だと、毎年10万円の配当金を受け取っても、税金で差し引かれて8万円しか再投資に回すことができません。しかし、新NISA口座では10万円全額を再投資に回すことができます。税金の有無によって最終的に資産形成のスピードに差が生まれますが、長期投資では、この差が拡大していきます。
新NISAで配当金が非課税になることは、税金の節約だけでなく、資産形成にも影響を与えます。
新NISAで配当金が非課税になる条件
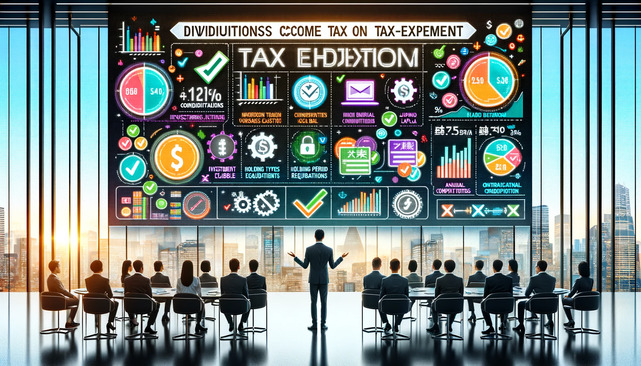
新NISA制度を利用して配当金を非課税で受け取るためには、成長投資枠を利用する必要があります。また、「株式数比例配分方式」の選択が必要になります。
そこで、新NISAで配当金が非課税になる条件について詳しく解説していきます。
配当株に投資できるのは成長投資枠のみ
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 投資対象商品 | 上場株式 投資信託 ETF(上場投資信託) REIT(不動産投資信託) | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠が存在し、それぞれ投資対象商品が異なります。
新NISAで配当金を受け取るためには、成長投資枠で上場株式に投資する必要があります。この投資枠を活用することで、配当金に対する非課税の恩恵を受けることができます。
つみたて投資枠では個別株に投資することができず、配当金を非課税で受け取ることができません。注意しましょう。
株式数比例配分方式を選択する
新NISAで配当金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
株式数比例配分方式とは、保有している株数に応じて、配当金を証券会社口座で受け取る方法です。
株式数比例配分方式以外にも、「配当金領収書方式」や「登録配当金受領口座方式」と呼ばれる受け取り方法がありますが、これらを選択すると、配当金に約20%の税金が課税されてしまいますので、注意が必要です。
新NISAで配当金を非課税で受け取るためにも、株式数比例配分方式を選択するようにしましょう。
新NISAで配当金や分配金が非課税になる投資商品

新NISAは、投資家が株式や投資信託に投資する際の税負担を軽減し、長期的な資産形成を支援します。
この制度は投資商品から得られる配当金や分配金も非課税となりますが、どのような投資商品が対象となるのか、詳しく解説します。
国内株式
新NISAでは、国内株式に投資することで、配当金は非課税となります。
例えば、大手の電機メーカーや金融機関に投資した場合、その企業から支払われる配当金は非課税となり、全額手元に利益として残すことができます。
新NISAを活用して国内株式に投資をすれば、配当金収入を増やしつつ税負担の軽減による恩恵を受けることができます。
外国株式
新NISAでは、外国株式から得られる配当金も、非課税の対象となります。そのため、配当金の税負担を気にすることなく、グローバル企業の成長に投資することができます。
新NISAを利用して米国株から配当金を得たとき、日本での税金はかかりません。しかし、米国での10%の税金は支払うことになります。
新NISAを活用することで税金は安くはなりますが、米国株の配当金にかかる税金はゼロにできない点は押さえておきましょう。
詳しくは、新NISAで米国株投資!非課税で配当金を受け取る方法とは?で解説しています。
投資信託やETF
投資信託やETF(上場投資信託)から得られる分配金も、新NISAで投資した場合、非課税となります。
分配金とは、投資信託の運用で得られた収益を投資家に配分したものです(株式の配当金に相当するもの)。
幅広い業種や地域に投資するグローバル株式ファンドや、安定した収益を目指す債券ファンドなど、これらのファンドから得られる分配金が、新NISAを利用することで非課税になります。
新NISAで高配当株を選ぶポイント

新NISAで高配当株を選ぶ際の重要なポイントは、配当利回りの高さ、企業の業績の安定性、そして財務の健全性になります。
これらの要素を総合的に判断することで、賢い高配当株投資が行えるようになります。
そこで、この3つのポイントについて解説します。
配当利回り
高配当株を選ぶ際には、配当利回りを確認しましょう。
配当利回りとは、企業が株主に支払う配当金の額を、その株の価格で割ったものです。つまり、投資した金額に対してどれだけのリターンがあるかを示します。
例えば、年間3千円を支払う企業の株式を10万円で購入した場合、配当利回りは3%になります。一方、年間6千円を支払う企業の株式を10万円で購入した場合、配当利回りは6%になります。
3千円(配当金)÷10万円(株価)=0.03 → 配当利回り3%
6千円(配当金)÷10万円(株価)=0.06 → 配当利回り6%
配当利回りが高いほど、投資金額に対してより多くの配当金を受け取ることができます。
業績の安定性
企業は業績が悪化すると、配当金の支払いを減額したり、停止したりすることがあります。
高配当株を選ぶ際には、業績も確認しましょう。業績が安定している企業は、将来にわたって配当金を支払う可能性が高く、長期投資に向いています。
新NISAを活用して投資する場合、業績が安定している企業を選ぶことで、経済環境の変化に強く、配当金を安定して確保することができます。
財務の健全性
高配当株を選ぶ際には、財務の健全性についても確認が必要です。財務が健全な企業は、資金繰りが安定しており、将来にわたって安定して配当金を支払う可能性が高くなります。
財務の健全性を評価する上で見るべきポイントには、自己資本比率、負債比率、流動比率などがあります。これらは、企業がどれだけ健全な財務構造を持っているか、つまり、どれだけ長期的に安定して経営できるかを表す指標となります。
自己資本比率
企業の財務の安定性を示す指標。この数値が高いほど、財務は健全である。
負債比率
企業の借金の割合を示す指標。この数値が低いほど、財務は健全である。
流動比率
企業の短期的な資金繰りを示す指標。この数値が高いほど、資金繰りが健全である。
例えば、自己資本比率が高く、流動比率が高い企業の場合、経済環境が悪化しても自社の資金でカバーできるため、配当を継続しやすいと言えます。
企業の財務状況については、決算書などを参考にして確認するようにしましょう。
新NISAでおすすめの高配当株5選

新NISAを活用した高配当株投資は、長期的な資産形成の有効な戦略となります。
ここでは、特におすすめの高配当株を5つ選んで、その魅力を簡単にご紹介します。
みずほフィナンシャルグループ(配当利回り:3.61%)
みずほフィナンシャルグループは、日本の大手銀行の一つで、安定した経営基盤を持っています。金融業界は一般的に安定した配当金を支払うことで知られており、みずほも例外ではありません。
新NISAの非課税メリットを活かしながらみずほフィナンシャルグループを長期保有することは、資産形成を行う上で魅力的な銘柄と言えます。
日本たばこ産業(JT)(配当利回り:4.98%)
日本たばこ産業(JT)は、高い配当利回りと安定した業績が特徴の銘柄です。
JTは、たばこ製品だけでなく、食品や医薬品など幅広い分野で事業を展開しているグローバル企業です。ほぼ独占市場でビジネスを展開し、不況に強く、安定した配当金収入が期待できます。
新NISAの非課税メリットを最大限に活かすためにも、JTは魅力的な銘柄と言えます。
三菱HCキャピタル(配当利回り:3.56%)
三菱HCキャピタルは金融サービスを提供する大手企業で、リース、オートローン、不動産ファイナンス、国際ビジネスなど多岐にわたる事業を展開しています。金融セクターの企業は一般的に、経済の波に強いため、配当利回りが高い傾向にあります。
同社は、多様な金融サービスを通じて安定した収益を生み出しています。また、グローバルな事業展開も進めており、将来の成長性に期待することができます。
三菱HCキャピタルは新NISA制度を活用し、非課税で配当金収入を得たい投資家にとって、非常に魅力的な銘柄と言えます。
キヤノン(配当利回り:3.45%)
キヤノンはカメラやプリンターなどのイメージング製品から、医療機器、産業機器、さらにはオフィス機器に至るまで、広範囲にわたる製品を提供しています。この多様な製品ラインナップが、安定した収益を生み出す基盤となって働いています。
また、同社は健全な財務状態を維持し、安定したキャッシュフローを生み出しています。この財務の健全性が、配当金の支払いを可能にしています。
以上の点から、キヤノンは新NISAを活用して配当金収入を得たい投資家にとって、非常に魅力的な銘柄と言えます。
三井住友フィナンシャルグループ(配当利回り:3.25%)
三井住友フィナンシャルグループは、日本を代表する大手銀行グループの一つです。同社は国内だけでなく、海外での事業展開も積極的に行っており、その多角的な事業構造からも安定した収益を期待することができます。
また、配当利回りも他の金融機関と比べて高く、2023年度は過去最高の売上高を記録しました。
三井住友フィナンシャルグループ株は、新NISAを利用して非課税で高い配当金収入を目指す投資家にとって、魅力的な銘柄と言えます。
新NISA口座の開設方法

新NISAを利用するためには、まず専用の口座を開設する必要があります。
ここでは、新NISA口座の開設方法と、どの金融機関で開設できるのかを解説していきます。
口座開設ができる金融機関
新NISA口座は、銀行、証券会社、信託銀行など、多くの金融機関で開設することができます。
例えば、新NISA口座が開設できる金融機関は次の通りです。
| ネット証券 | ・SBI証券 ・楽天証券 ・マネックス証券 ・GMOクリック証券 ・松井証券など |
| 大手証券 | ・野村證券 ・日興証券 ・大和証券 ・みずほ証券 ・SMBC日興証券など |
| 大手銀行 | ・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・ゆうちょ銀行など |
| 信託銀行 | ・三菱UFJ信託銀行 ・みずほ信託銀行 ・りそな信託銀行など |
| 信用金庫 | ・全国信用金庫協会 |
| 農協 | ・JAバンク |
口座開設の手続きは、各金融機関のウェブサイトや店舗で行うことができます。
金融機関によって取扱商品やサービス内容が異なるため、よく比較検討した上で自分に合ったところを選びましょう。
口座開設方法
新NISA口座の開設方法は、ウェブサイトまたは店頭で手続きすることができます。
ウェブサイトや店頭での口座開設の手続きは、次の通りです。
手順1. 金融機関のウェブサイトにアクセスし、新NISA口座開設のページへ行く
↓
手順2. 必要な情報を入力し、必要書類をアップロードする
↓
手順3. 手続き完了後、口座開設の承認を待つ
手順1. 最寄りの金融機関の支店を訪れる
↓
手順2. 口座開設に必要な書類を持参し、担当者に手続きを依頼する
↓
手順3. 担当者の説明を聞きながら、申込書に必要事項を記入する
↓
手順4. 手続き完了後、口座開設の承認を待つ
新NISA口座の開設方法には、ウェブサイトで申し込む方法と店頭で申し込む方法がありますので、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
新NISAで配当金も非課税になる仕組みについてよくある質問

最後に、新NISAで配当金も非課税になる仕組みについてよくある質問をまとめました。
新NISAとは何ですか?
新NISA(ニーサ)は、2024年1月にスタートした日本の小額投資非課税制度です。
この制度は株式や投資信託などの売却益や配当金が非課税となり、投資家にとって大きなメリットを提供します。
新NISAで配当金も非課税とはどういうことですか?
新NISAでは、投資によって得られる利益(売却益)だけでなく、株式などから得られる配当金にも税金はかかりません。
通常、配当金には20.315%(国税15.315%+地方税5%)の税金がかかりますが、新NISA口座を利用することで、この税金が非課税となります。
新NISAを利用するための条件はありますか?
新NISAを利用するためには、まず証券会社などの金融機関で新NISA口座を開設する必要があります。
新NISAは一人一口座の制限があるため、複数の金融機関で口座を持つことはできません。また、非課税枠が設けられており、その範囲内での投資が非課税扱いになります。
新NISAで配当金も非課税になる条件とおすすめの高配当株のまとめ
新NISA制度で配当金を非課税で受け取るには、成長投資枠を利用し、株式数比例配分方式を選択する必要があります。
成長投資枠では上場株式に投資することができ、配当金を受け取ることができます。一方、つみたて投資枠では上場株式に投資することはできません。
株式数比例配分方式を選ばずに他の受け取り方法を選択すると、配当金に約20%の税金が課税されるため、注意が必要です。
新NISAでおすすめの高配当株は、次の通りです。
- みずほフィナンシャルグループ(配当利回り:3.61%)
- 日本たばこ産業(JT)(配当利回り:4.98%)
- 三菱HCキャピタル(配当利回り:3.56%)
- キヤノン(配当利回り:3.45%)
- 三井住友フィナンシャルグループ(配当利回り:3.25%)
新NISAを上手く活用し、配当金で資産形成を目指しましょう!