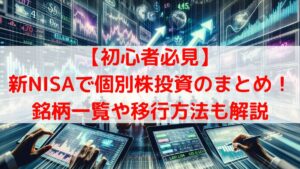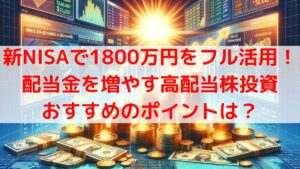2024年1月から新NISAがスタートしました。新NISAでは、株式や上場投資信託(ETF)などの投資で得られた配当金や分配金が非課税になります。特に高配当ETFへの投資は、安定した分配金を得ることができます。
今回は、新NISAの仕組みと高配当ETFの特徴、配当金や分配金の非課税となる条件、高配当ETFの選び方とおすすめ銘柄、新NISA口座でETFを購入する手順などについて解説します。
この記事を読めば、新NISAを活用した高配当ETF投資の基礎知識が身につき、非課税のメリットを最大限に生かした投資戦略を立てることができるようになります。初心者の方でも高配当ETF投資に必要な知識が学べるように解説していますので、最後までご覧ください。
配当金と分配金の違いについて
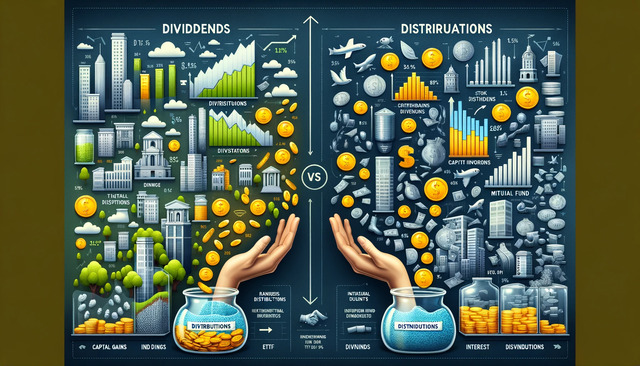
投資を行う場合、定期的に受け取れる収入には配当金と分配金があります。
配当金は株式を保有する投資家に対して、企業の利益の一部が支払われるものです。一方、分配金は投資信託などの投資商品から得られる利益になります。
そこで、配当金と分配金の違いについて、詳しく解説します。
配当金とは?
配当金とは、株式を保有する投資家に対して会社から支払われる利益の一部です。企業が儲かったとき、その利益を株主に還元する形で支払われます。
企業は利益の一部を内部留保し、残りを株主に配当金として支払います。配当金は利益に連動していることが多く、企業業績が良ければ配当金も増える傾向があります。
もし、ある企業の株式を100株保有していて、その企業が1株につき10円の配当金を支払った場合、あなたは1000円の配当金を受け取ることになります。
配当金は、企業のオーナーとして、その利益を共有する方法です。
分配金とは?
分配金とは、投資信託やETFなどから得られる利益のことです。
投資信託は、多くの投資家から集めたお金をプロのファンドマネージャーが株式や債券などに投資し、その運用結果によって得られた利益を投資家に分配します。
分配金には、運用による値上がり益、配当金、利子などの他に、投資元本の一部まで含まれている可能性があります。例えば、投資信託に10万円を投資したとして、1年間の運用で5%の利益が出た場合、5000円が分配金として支払われます。しかし、この分配金には運用利益だけでなく、元本が含まれていることもあります。
高配当ETFとは?
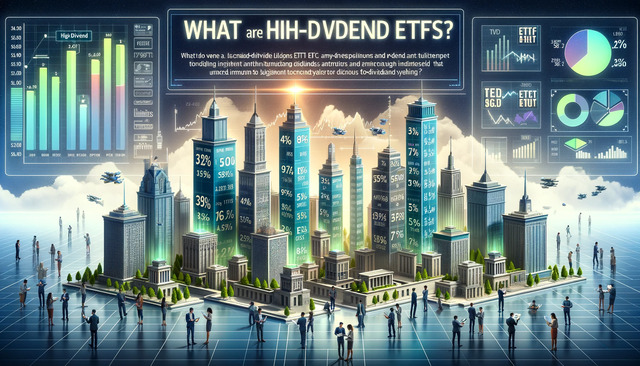
高配当ETF(Exchange Traded Fund)とは、高配当株に投資する上場投資信託です。このETFは、複数の高配当株をバスケットで持っており、その平均配当利回りを反映します。また、複数の高配当株式に分散投資しているため、一つの銘柄に集中投資するよりもリスクを低減することができます。
例えば、個別の高配当株に投資する場合、その銘柄の業績が悪化すれば配当金が減額または停止になる可能性があります。しかし、高配当ETFは複数の銘柄に分散投資しているため、ある銘柄の配当金が減額されても、他の銘柄の配当金でカバーすることができます。
高配当ETFは、高配当株の利点を享受しつつ、リスク分散を図りたい投資家におすすめの投資商品です。
新NISAで配当金や分配金が非課税になる仕組みについて

通常、投資で得た利益には約20%の税率が適用されます。しかし、新NISAを利用することで、税金を支払う必要がなくなります。
また、新NISAの「成長投資枠」を活用することで、株式やETFなどの投資商品から得られる配当金や分配金が全額非課税となり、年間240万円までこの優遇を受けられるようになります。
投資にかかる税金
投資をするとき、通常は利益に対して税金がかかります。株式投資の場合、配当金に対して約20%の税率が適用されます。同様に、ETFからの分配金も同じ税率が適用されます。
例えば、年間で10万円の配当金や分配金を得た場合、そのうち約20%にあたる2万円が税金として課税され、手取りは8万円となります。
新NISAを活用すれば配当金や分配金は非課税
新NISA制度を利用することで、配当金や分配金が非課税になります。この制度は、個人が中長期的に資産形成することを支援するために設けられました。
上記の例で、新NISA口座を使って同じ10万円の配当金や分配金を得た場合、全額が非課税となるため、2万円の税金を支払う必要がありません。その結果、手元には10万円全額が残ります。
新NISA制度を利用すれば、配当金や分配金からの収入は非課税で受け取れるため、節税効果が得られるのです。
株式やETFに投資するなら成長投資枠を活用
新NISA制度では、株式やETFなどに投資する場合、「成長投資枠」を設けています。この枠内での投資によって得られる配当金や分配金は非課税となり、年間240万円までの投資が可能になります。
「つみたて投資枠」でもETFに投資することは可能ですが、2024年1月時点ではわずか8本だけと限定的です。また、この投資枠に対するETFの採用条件が厳しいため、取り扱う販売会社が少ないのが現状です。そのため、ETFに投資するなら、取り扱い数が多い「成長投資枠」が適切となります。
新NISAで高配当ETFに投資するメリット

新NISAで高配当ETFに投資することで、以下のメリットを得ることができます。
- 投資信託よりもコストが低い
- 複数の銘柄に分散投資できる
- 株式のように銘柄分析の必要がない
- 債券やREITなどにも投資できる
そこで、それぞれのメリットについて詳しく解説します。
投資信託よりもコストが低い
高配当ETFへの投資は、投資信託に比べて運用コストが低く抑えられています。
ETFの運用コストは、年間の運用資産額に対する割合(経費率)で示されますが、パッシブ運用のため、この経費率は一般的に低く設定されています。
投資信託よりもコストが低い高配当ETFは、長期投資においてより多くの収益を期待することができます。
複数の銘柄に分散投資できる
高配当ETFは投資信託と同じように、一つの商品を購入することで、複数の高配当株に自動的に分散投資することができます。そのため、個別銘柄に集中投資するよりもリスクが低くなります。
もし個別銘柄に集中投資した場合、業績が悪化すれば、配当金の支払いは停止になる恐れがあります。しかし高配当ETFは、複数の銘柄に分散投資しているため、特定の銘柄に過度に依存することがありません。
高配当ETFには分散投資効果があり、個別銘柄のリスクを低減するメリットがあります。
株式のように銘柄分析の必要がない
高配当ETFに投資するもう一つのメリットは、個別の銘柄分析を行う必要がないことです。
株式投資の場合、企業の業績や成長性、財務状況などを詳細に分析する必要があります。しかしETFはプロのファンドマネージャーによって運用されるため、そうした分析作業は必要ありません。
高配当ETFへの投資は、特に投資初心者や忙しい投資家にとって、おすすめの投資方法です。
債券やREITなどにも投資できる
新NISAでは、高配当ETFを通じて株式だけでなく、債券やREIT(不動産投資信託)など多様な資産クラスにも投資することができます。そのため、より広範な分散投資ができます。
株式、債券、REITなどは、違う値動きをします。例えば、株式市場が不安定なときには、債券やREITが安定した値動きをすることがあります。
ETFには単一の資産クラス(株式など)だけでなく、複数の資産を組み合わせた商品も存在します。このようなETFに投資することで、一つの商品で複数の資産に分散投資することができます。
新NISAで高配当ETFに投資するデメリット
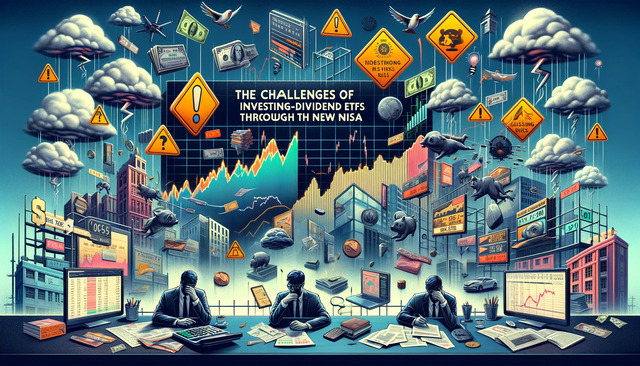
新NISAで高配当ETFに投資することで、多くのメリットがあります。しかし、いくつかのデメリットもあります。
新NISAで高配当ETFに投資するデメリットには、以下のようなものがあります。
- 値動きが激しい商品が多い
- 分配金が減額されるリスクがある
- 個別株よりもリターンが低い
そこで、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
値動きが激しい商品が多い
高配当ETFは、高い配当利回りを実現するため、株価の値動きが大きくなりがちな銘柄に投資している場合があります。
例えば、ある高配当ETFに、配当利回りが6%を超える景気敏感株や小型株が複数組み入れられていたとします。景気減速時には株価が下落するリスクがあり、その結果、元本割れが生じる可能性があります。
分配金が減額されるリスクがある
ETFの分配金は、組み入れ銘柄から支払われた配当金が原資となっています。そのため、組み入れ銘柄の業績悪化で配当金の支払いが減額または停止された場合、ETF全体の分配金も減ることになります。
例えば、10銘柄で構成された高配当ETFから10万円の分配金を受け取っていたとします。そのうち5銘柄が業績悪化で配当金の支払いを停止した場合、分配金が5万円に減額される恐れがあります。
このように、高配当ETFへの投資では、予定されていた通りに分配金が支払われない可能性もあるため、減額されてしまうリスクに十分注意することが必要です。
個別株よりもリターンが低い
ETFのような分散投資にはリスクを抑える効果がありますが、その代わり特定の株式が大きく値上がりしたときの恩恵を受けにくくなります。一方で、個別株投資は高いリスクを伴いますが、選んだ銘柄のパフォーマンスによっては高いリターンを得るチャンスもあります。
例えば、石油株が大きく成長した場合、そのセクターに集中投資した投資家は大きなリターンを得ることができます。しかし、幅広い分野に分散投資している高配当ETFでは、そのセクターの成長が全体のリターンに与える影響は限定的であるため、大きなリターンを期待することができません。
高配当ETFを選択する場合、リスクを抑えつつ安定したリターンを目指す一方で、個別株式投資に比べて大きなリターンを逃す可能性があります。
非課税で分配金を受け取るためには株式数比例配分方式を選択

新NISA口座で分配金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。
受け取り方法の変更は、証券会社のウェブサイトから簡単に設定することができます。
株式数比例配分方式とは
「株式数比例配分方式」とは、株式の配当金、ETFやREITの分配金を証券会社の取引口座で受け取る方法のことです。この方式を選択することで、配当金や分配金が非課税となります。
株式数比例配分方式の他にも、「配当金領収書方式」や「登録配当金受領口座方式」などといった受け取り方法がありますが、これらを選択すると、配当金や分配金に対して税金が課税されます。
配当金や分配金を非課税で受け取るためにも、必ず「株式数比例配分方式」を選択しましょう。
新NISA口座で分配金の受取方法を「株式数比例配分方式」に変更する方法
新NISA口座で分配金を非課税で受け取るためには、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。この手続きを行うには、証券会社のウェブサイトにログインし、「口座設定」または「取引設定」メニューから「株式数比例配分方式」を選ぶ必要があります。
詳しい設定手順については、新NISAで配当金を非課税で受取方法は?株式数比例配分方式の変更方法で紹介していますので、そちらをご確認下さい。
ETFの分配金の支払時期や権利確定日はいつ?
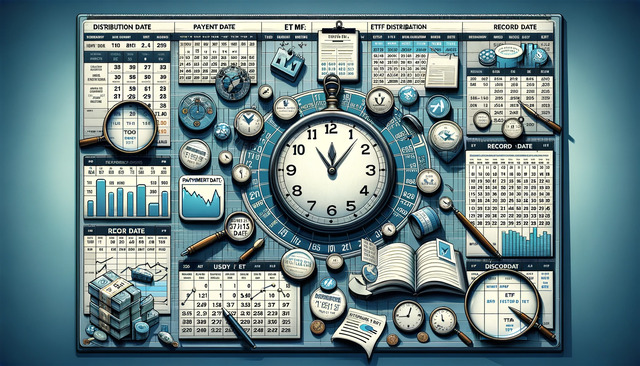
ETFの分配金の支払いは、運用会社の方針によって、年に2回から4回の間で支払われます。特に重要なのが「権利確定日」で、この日にETFを保有していることで、分配金を受け取ることができます。
そこで、分担金の支払い時期と権利確定日について詳しく解説します。
分配金の支払い時期
ETF(Exchange-Traded Fund)からの分配金の支払いは、運用会社の方針によって異なります。多くのETFでは、年2回(中間期末と決算期末)または年4回(四半期ごと)に分配金を支払う仕組みになっています。
ETFに投資をする際には、分配金の支払時期を事前に確認するようにしましょう。
権利確定日
権利確定日とは、分配金を受け取る権利があるかを決定する日のことで、この日にETFを保有していると、分配金を受け取ることができます。つまり、権利確定日にETFを保有している投資家にのみに分担金が支払われます。
例えば、あるETFの権利確定日が3月31日であった場合、その日にETFを保有している投資家は分配金の支払い対象となります。もし権利確定日の翌日にETFを購入した場合、その分配金の支払いは受けられません。
分配金を受け取るためには、ETFの権利確定日を把握し、その日までにETFを保有しておくことが必要です。
高配当ETFの選び方

高配当ETFを選ぶ際には、配当利回りの高さや信託報酬の低さなど、いくつかのポイントがあります。
そこで、新NISAで高配当ETFを選ぶ際のポイントや注意点について、詳しく解説します。
配当利回りの高さ
高配当ETFを選ぶ際、最初に注目すべき点は配当利回りの高さです。配当利回りとは、1年間に支払う予想配当額を現在の市場価格で割ったもので、この数値が高いほど投資効率が高くなります。
例えば、年間の配当利回りが6%のETFと3%のETFがあった場合、6%のETFを選べば、同じ投資金額で2倍の分配金を受け取ることができます。
信託報酬の低さ
高配当ETFを選ぶ際のもう一つの重要な要素は、信託報酬の低さです。信託報酬は、ETFの運用にかかる年間の費用であり、この数値が高いほど、投資家にとって大きなコストとなります。
例えば、年間の信託報酬が0.2%のETFと0.5%のETFがあった場合、長期的に見ると0.2%の方がより多くの収益をもたらします。
長期投資を考える場合、信託報酬の低いETFを選択することで、費用を抑えつつ収益性を高めることができます。
流動性の高さ
高配当ETFを選ぶ際には、流動性の高さを確認することが重要です。流動性が高いということは、市場での売買が活発に行われており、投資家が買いたい時にすぐ買え、売りたい時にすぐに売ることができる状態です。
流動性が低いETFは売買が困難になり、売りたいときに希望した価格で売れない可能性があります。
高配当ETFを選ぶ際は、出来高や時価総額などから流動性を確認するようにしましょう。
目論見書を確認
高配当ETFを選ぶうえで、目論見書を確認することも非常に重要です。目論見書を確認することで、ETFの運用方針やコスト、リスクを正確に把握し、適切な投資判断を行うことができます。
例えば、投資対象となる資産の種類、分配金の支払い頻度などは、目論見書に詳しく記載されています。これらの情報を確認することで、自分の投資スタイルに合った高配当ETFを見つけることができます。
高配当ETFを選択する前に、必ず目論見書を確認し、運用方針やコスト、リスクなどを総合的に考慮した上で投資判断を行うことが重要です。
GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式(2564)−交付目論見書
GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式(2564)−請求目論見書
大まかなに把握したい場合は、交付目論見書で確認をしましょう。
詳しく把握したい場合は、請求目論見書で確認しましょう。
おすすめの高配当ETF銘柄一覧

新NISAの「成長投資枠」で選べるETFは、現在280本あまりになります。その中から、高配当ETFを選ぶのはなかなか大変です。
そこでおすすめの高配当ETFについて、その特徴や魅力、さらに配当利回りについてご紹介します。
GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式(配当利回り:3.73%)
GX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式(2564)は、MSCI日本株高配当指数に連動するようになっています。同指数は、国内の上場株式の中から配当利回りの高い銘柄を選んで構成されており、高配当株への分散投資が行われています。
このETFの2024年3月時点の組入上位銘柄は、川崎汽船や石油資源開発などの高配当株が中心となっています。
分散投資によってリスク低減も図れるため、投資初心者におすすめのETFです。
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF(配当利回り:3.10%)
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)は、日本の優良高配当株に分散投資ができる人気の高配当ETFです。
この ETFは、日経平均株価の構成銘柄の中から配当利回りが高い上位50銘柄に絞っています。組入銘柄は毎年入れ替わり、常に高配当銘柄のみに絞り込まれています。
2023年3月時点の組入上位銘柄は、日本たばこ産業、東京海上ホールディングス、三菱UFJフィナンシャルなどの優良大手企業の高配当株が中心です。配当利回りは3%前後と魅力的な水準となっています。
(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF(配当利回り:2.99%)
(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF(1577)は、日本株の中から配当利回りが高い上位70銘柄に分散投資できるETFです。
このETFは、日本の全上場銘柄から業種や規模を問わず、配当利回りが高い順に70銘柄を選んでいます。
2023年3月時点の組入上位は、日本ハムファクトリー、三菱商事、ヤマトHDなどの銘柄が組み込まれています。また、信託報酬は年率0.3672%と平均的な水準です。
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル(配当利回り:3.23%)
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル(1499)は、高配当株に投資しつつ、リスクヘッジをする工夫がされた特殊なETFです。
このETFは高配当70銘柄への投資に加え、TOPIXの動きをヘッジするためのショート投資を並行して行うことで、TOPIX全体の値動きのリスクを排除しつつ、高配当株のパフォーマンスのみを享受できる仕組みになっています。
安定した配当収入とリスクを避けたい投資家に、おすすめのETFです。
新NISAで高配当ETFを購入する手順
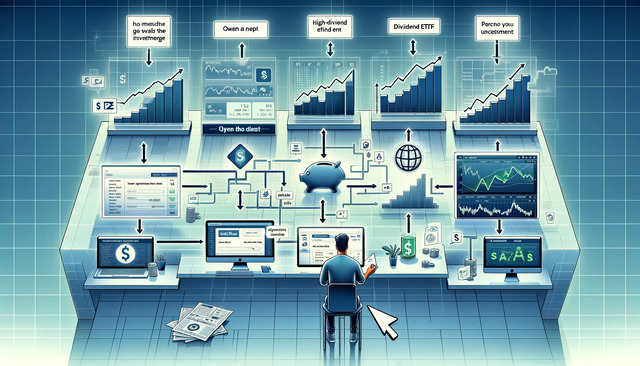
新NISA制度を利用して高配当ETFを購入するためには、まず専用の新NISA口座を金融機関で開設することから始まります。
口座開設後、インターネット取引を通じて自身の投資目標やリスク許容度に合った高配当ETFを購入します。
そこで、新NISA口座の開設からETFを購入するまでの手順について解説します。
NISA口座を開設する
新NISAで高配当ETFを購入するためには、専用の口座を開設する必要があります。新NISA口座は、大手銀行や証券会社などの金融機関で開設することができます。
口座開設の際には、運転免許証やマイナンバーカードなどの書類が必要になります。必要書類は金融機関によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、口座開設の方法には、金融機関の窓口で直接申し込む方法と、ホームページなどのオンラインで申し込む方法があります。自分に合った方法で申し込みましょう。
ETFを購入する
新NISA口座を開設した後は、投資対象となる高配当ETFを選んで購入します。
ETFの購入手順は、次の手順で行います。
ETFを選ぶ際には、配当利回り、信託報酬、過去の実績などを比較検討し、自身のリスク許容度と投資目標に合った高配当ETFを選択することが重要になります。
新NISAでETFの配当金についてよくある質問

最後に、新NISAでETFの配当金についてよくある質問をまとめました。
新NISAとは何ですか?
新NISA(旧NISAの改正版)は、日本の個人向け投資促進制度で、投資した際の利益が非課税になる制度です。
2024年1月にスタートし、これまでより長期的な資産形成をサポートします。
ETFとは何でしょうか?配当金はどのように関係していますか?
ETF(Exchange Traded Fund)は、株式や債券など複数の資産を組み入れた投資信託で、証券取引所で株式のように取引されます。
ETFから得られる分配金の中には、株式投資によって得られた配当金などが含まれており、それを投資家に還元します。
新NISAでは、ETFから得られる分配金も非課税の対象となります。
投資初心者が新NISAを利用してETFに投資するメリットは何ですか?
投資初心者にとって、新NISAを利用してETFに投資する最大のメリットは、税制面の優遇です。特に、分配金と売却時の利益が非課税になるため、長期的に資産を増やすことができます。
また、ETFは複数の資産に分散投資されているため、個別銘柄への投資に比べてリスクを抑えることができます。
新NISAで高配当ETFの選び方についてのまとめ
新NISAで高配当ETFを選ぶ際の主なポイントは、次の通りです。
配当利回りの高さ
配当利回りが高いETFほど、同じ投資金額で多くの分配金を受け取ることができます。
信託報酬の低さ
信託報酬が低いETFほど、長期的に見ると高い収益性が見込めます。
流動性の高さ
流動性が高いETFほど、売買がスムーズに行えます。
目論見書の確認
目論見書を確認し、ETFの運用方針、コスト、リスクを総合的に検討することが重要です。
これらのポイントを考慮しながら、自分の投資スタイルに合った高配当ETFを選ぶことが重要です。