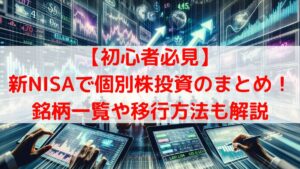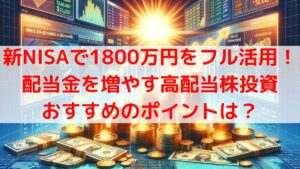新NISAがスタートしましたが、多くの投資家が年間360万円の投資枠を最大限に活用する方法について調べています。
今回は、年間360万円の投資枠を5年続けて有効活用するために、360万円の投資計画と5年間の投資戦略について解説。さらに投資枠を賢く使うため、個別株や投資信託の選び方、おすすめの投資商品について詳しく解説します。
この記事を読めば、新NISAを利用した賢い投資戦略を学ぶことができ、自分自身の投資計画をより具体的に立てることが可能となりますので、最後までご覧ください。
新NISAの概要

新NISAは2024年から始まった、個人投資家の投資活動を支援する新しい税制優遇措置です。
新NISAでは、より柔軟かつ長期的な投資が可能となり、投資家にとって有利な制度となっています。
新NISAとはどのような制度なのか、詳しく見ていきます。
新NISAとは?
新NISAは投資の非課税枠を拡大し、非課税期間を無期限にした新しい制度です。これにより、個人投資家は長期的な視点で資産形成を行うことができます。
また、成長投資枠とつみたて投資枠という2つの投資枠があり、それぞれの投資目的に応じて使い分けることが可能となっています。
成長投資枠
年間投資枠は240万円。主に上場株式や投資信託などに投資することができる
つみたて投資枠
年間投資枠120万円。長期の積立・分散投資に適した投資信託が対象
非課税枠と非課税期間
新NISAの大きな特徴は、非課税枠の大きさと非課税期間の無期限化になります。
非課税保有限度額
最大1800万円(うち成長投資枠で最大1200万円)
非課税期間
無期限
例えば、成長投資枠で個別株に投資をした場合、株価上昇後に売却をしても利益は非課税扱いとなります。これは、長期的な資産形成を目指す個人投資家にとって大きなメリットです。
また、保有する資産を売却した場合、その分の非課税枠が翌年度以降に復活し、柔軟な資産運用が行えます。
新NISAはより幅広い投資選択肢と長期的な資産形成を可能にする、魅力的な制度となっています
旧NISAと新NISAの違い
旧NISAと新NISAの主な違いは、年間投資枠と非課税期間にあります。
2つの制度の違いは、次の通りです。
| 旧NISA | 新NISA | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 |
一般NISA:120万円 つみたてNISA:40万円 |
成長投資枠:240万円 つみたて投資枠:120万円 |
| 非課税期間 |
一般NISA:5年 つみたてNISA:20年 |
無期限 |
| 非課税保有限度額 |
一般NISA:最大600万円 つみたてNISA:最大800万円 |
成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて最大1800万円 |
旧NISAの場合、一般NISAの年間投資枠は120万円、つみたてNISAは40万円でした。しかし新NISAでは、成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が120万円となっています。
また旧NISAの場合、非課税期間は一般NISAは5年、つみたてNISAは20年まででした。しかし新NISAでは、非課税期間が無期限となります。
この制度の変更により、新NISAでは多くの資金を長期にわたって非課税で運用することが可能となります。
新NISAの注意点やリスク

新NISA制度は多くの投資家にメリットを提供しますが、注意すべきリスクや注意点も存在します。
特に投資初心者は、次の点をしっかりと理解する必要があります。
必ず利益が出るわけではない
投資には常にリスクが伴います。新NISAで投資をしたからといって、利益が保証されているわけではないことを理解することが重要です。
投資でハイ・リターンな商品に投資をした場合、それに伴ってリスクが高くなります。例えば個別株に投資した場合、株式市場が好調なら株価が上昇し、大きな利益を獲得することができます。しかし、世界的なパニックが起こって株式市場が悪くなれば、株価が下落して損失を被る恐れがありあります。
投資信託も同様に、市場によって影響されるため、必ずしも安定した利益が獲得できるわけではありません。
投資で利益を得るためには、市場の動向を注視し、長期的な視点で投資を続けることが重要になります。
元本割れを起こす場合もある
新NISAを利用しても、元本割れのリスクがあります。
例えば、特定の産業に偏った投資を行った場合、その産業が不振に陥れば株価が下落して元本割れを起こす可能性があります。また、銘柄の選定ミスや、市場の急激な変化によっても、同様のリスクが発生します。
市場の短期的な動きには注意し、分散投資によってリスクを分散させることが重要です。
投資は自己責任
投資は常に自己責任です。新NISAを活用する際も、この原則は変わりません。
例えば、自分がよく理解していない商品に投資をすることは避けるべきです。投資する前には市場の動向、投資対象商品の特性など、十分な情報収集と分析が必要です。
また、市場の一時的な動きに惑わされず、自分自身の投資目的を堅持することが重要です。投資顧問や専門家の意見も参考にしつつ、最終的な判断は自分で行う必要があります。
投資の基本原則を忘れず、リスク管理を徹底することが、成功へのカギとなります。
新NISAで毎年360万円を5年間どのように投資するべきか

新NISAの制度を活用して、毎年360万円を5年間投資する際の計画を立てる場合には、長期的な視点で継続することや、市場動向の分析、定期的なポートフォリオの見直しが必要になります。
そこで、360万円の投資計画と5年間の投資戦略について解説します。
360万円の投資計画
新NISAを利用して毎年360万円を投資する際、以下の3つについて計画を立てることが重要になります。
手順1.毎月の投資額
↓
手順2.分散投資
↓
手順3.リスク管理
それでは、それぞれの手順について順番に解説します。
手順1.毎月の投資額
360万円を5年間投資し続ける場合、毎月いくらずつ投資をするか計画を立てます。
計画案として例えば、毎月30万円を投資する方法が考えられます。もしくは、年2回のボーナスのときにまとまった金額を投資する方法も考えられます。
手順2.分散投資
一つの銘柄や業界に偏ってしまうと、投資リスクが高くなります。
このようなリスクを避けるためにも、株式、投資信託、REITなど、複数の資産クラスに分散投資をします。
手順3.リスク管理
リスク許容度に応じて、リスクの高い資産とリスクの低い資産のバランスを考えながら投資を行います。
例えば、リスクの高い資産に投資を行う場合は、成長投資枠を活用して個別株などに投資を行います。またリスクの低い資産に投資を行う場合は、つみたて投資枠を活用して投資信託などに投資を行います。
5年間の投資戦略
新NISAで5年という期間を考慮した投資戦略を計画する際のポイントは、以下の通りです。
手順1.長期的な視点での継続
5年という中期的な投資期間を考慮し、短期的な市場の変動に一喜一憂してはいけません。長期的な視点で投資を継続することが大切です。
手順2.市場動向の分析
経済情勢や市場のトレンドを定期的に分析し、必要に応じてポートフォリオを調整します。
手順3.定期的な見直し
市場の変化に変化します。そのため、半年ごとに自分の投資ポートフォリオを確認し、状況に応じて調整を行いましょう。
新NISAで投資信託を選ぶポイント

新NISAを活用して投資信託を選ぶ際には、投資信託の種類、信託報酬、過去の運用実績をチェックする必要があります。
これらをしっかりとチェックし、自分に合った投資信託を選ぶことで、長期的な資産形成を目指すことができるようになります。
投資信託の種類
投資信託には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。
インデックスファンド
特定の市場指数に連動するように運用されるファンド。市場の平均リターンを目指して運用されます。
市場の成長に伴ってリターンも大きくなるため、長期投資に適しています。
アクティブファンド
ファンドマネージャーが積極的に運用を行い、市場の平均を上回るリターンを目指します。
市場の動向に応じて運用するため、高いリターンが期待できますが、リスクも伴います。
バランス型ファンド
株式と債券など、いくつかの異なる資産で運用されるファンドです。そのため、一つの投資信託で分散投資の効果が得られます。
インデックスファンドはアクティブファンドよりも信託報酬が安く、長期投資に適しています。
アクティブファンドは積極的に運用を行うため、信託報酬が高くなります。
バランス型ファンドは一つの投資で複数の資産に投資ができるため、分散投資の効果を得ることができます。そのため、初心者におすすめの投資信託です。
信託報酬
投資信託を選ぶ際には、信託報酬にも注意が必要です。
信託報酬とは、投資信託の運用にかかる費用です。この費用は、投資信託の純資産額から毎年一定の割合で徴収されます。
高い信託報酬はコストとなり、長期的に見るとリターンが低くなる可能性があります。
インデックスファンドは低コストで運用されることが多いため、初心者におすすめです。
過去の運用実績
過去の実績が良いファンドは、運用の質が高いと考えられます。そのため、これまでの運用実績も重要な選定基準の一つになります。
しかし、市場環境の変化によっては、過去の成績が必ずしも継続するとは限りません。
投資信託を選ぶ際には、複数の時期に渡って実績を比較することが重要です。
新NISAで投資信託を選ぶ際には、投資信託の種類、信託報酬、過去の運用実績などをチェックする必要があります。
このポイントをおさえ、自身のリスク許容度や投資目的に合った投資信託を選ぶことが重要です。
新NISAでおすすめの投資信託
新NISAでおすすめの投資信託は、次の3つです。
これらの投資信託は特定の国や地域に依存せず、世界経済の成長に連動するため、初心者から経験者まで幅広い投資家におすすめです。
また、低コストで分散投資を実現したい投資家には、特に最適な投資信託となっています。
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
「eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)」は、世界中の株式市場に分散投資を行う投資信託です。
世界各国の株式に幅広く分散投資を行うため、特定の国や地域に影響されない特徴があります。また世界経済の成長に伴って、このファンドも成長することが期待できます。
楽天全世界株式インデックスファンド
「楽天全世界株式インデックスファンド」は、低コストでグローバルな株式市場に投資できる投資信託です。
低い信託報酬で運用され、世界の主要な株式指数に連動するように設計されています。
全世界の株式市場に手軽に分散投資ができるため、初心者におすすめのファンドです。
セゾン資産運用全世界株式インデックスファンド
「セゾン資産運用全世界株式インデックスファンド」は、世界の株式市場に幅広く分散投資を行うファンドです。
このファンドの特徴は、世界の株式市場に幅広く投資を行うため、地域に偏らない分散投資を実現できることです。
世界の株式市場が全体的に好調なときには、このファンドもそれに連動して成長することが期待できます。
新NISAで個別株を選ぶポイント

新NISA制度を活用して個別株を選ぶ際には、いくつかのポイントをチェックする必要があります。
これらのポイントを理解し、自分に合った銘柄を選ぶことで、長期的な資産形成が可能となります。
企業のファンダメンタルズ
企業のファンダメンタルズを分析することで、その銘柄が投資対象として適正なのかを判断することができます。
企業のファンダメンタルズの分析ポイントは、以下の3つです。
財務の健全性
企業の財務諸表を分析し、資産や負債、収益性、キャッシュフローの状況などを評価します。
事業の成長性
企業が行う事業の将来性や市場の成長性を分析します。
業績の推移
業績の推移を確認し、売上高や営業利益は伸びているのか、しっかり利益を確保できているのかを確認します。
例えば、テクノロジー企業の場合、研究開発にかける費用や新製品の発表が業績に大きな影響を与えます。これらのポイントに問題がなくしっかりと伸びていれば、投資対象として魅力があると判断できます。
企業のファンダメンタルズに関する資料は、自社のホームページや決算プロなどから確認することができます。
株価の推移
株価の推移を分析することで、将来の株価を予測することができます。
過去の株価チャートやテクニカル分析などを活用することで、株価のトレンドを把握することができます。また、株価の推移を分析するためには、移動平均線やMACDなどのテクニカル指標を用いることが一般的です。
株価の推移は、証券会社のウェブサイトやYAHOO!ファイナンスなどで確認することができます。
配当金
企業の中には、配当金を出しているところもあります。そのような会社の株を持っていれば配当金がもらえるので、投資対象銘柄としては魅力があります。
そのときに確認したいことは、次の2つです。
配当の安定性
何年にもわたって継続して配当金を出している企業は、業績が安定しています。
配当利回り
高い配当利回りは、株価に対して配当金のリターンが高いことを表しています。
しかし配当利回りが高すぎる場合には、企業に何らかの問題があって株価が安くなっているのかもしれません。その場合は、企業のファンダメンタルズをチェックしてみましょう。
例えば、安定して配当金を出している企業には、大手企業や銀行などがあります。
新NISAでおすすめの個別株
新NISAでの投資におすすめの個別株には、トヨタ自動車、ソニー、任天堂が挙げられます。
これらの企業は、財務状況が良好で、世界的なブランド力を持つため、投資対象として魅力的な銘柄です。
トヨタ自動車
トヨタ自動車は、世界トップクラスの自動車メーカーです。世界各国で自動車を販売しており、近年は電動化や自動運転技術などの開発にも力を注いでいます。
財務体質も良好で世界的なブランド力も持ち合わせているため、投資対象としては魅力的な銘柄です。
ソニー
ソニーはエレクトロニクス、ゲーム、エンターテインメントの各分野で高い競争力を持っています。
PlayStationシリーズなどのゲーム事業は、世界中で安定した収益を生み出しており、特に新型コンソールの発売時は大きな注目を集めます。
2023年度の連結決算では、売上高11兆5千億円、営業利益1兆1700億円を計上しています。
ソニーは今後も成長することが期待でき、投資対象としては魅力的な銘柄です。
任天堂
任天堂は世界的なゲーム会社で、家庭用ゲーム機「スイッチ」や、スマートフォン向けゲーム「ポケモンGO」などが人気です。
スイッチなどのゲーム機と、マリオやゼルダといった人気のフランチャイズは、長期的に収益を生み出しています。
2023年度の連結決算は、売上高1兆6000億円、営業利益5000億円を計上。
任天堂は、今後も独創的なゲームソフトの開発を通じて、さらなる成長を目指していくと予想されます。
新NISA口座を開設できる金融機関

新NISAの口座は、様々な金融機関で開設することができます。
口座を開設する金融機関を選ぶ場合には、サービス内容や手数料、利便性などを比較検討することが重要です。
そこで、新NISA口座が開設できる主要な金融機関と、新NISAにおすすめの証券会社について解説します。
主要な金融機関の種類
新NISA口座を開設できる主要な金融機関は、以下の通りです。
大手銀行
大手銀行には三菱UFJ銀行やみずほ銀行などがあり、信頼性を重視したい方に適しています。また、専門家と直接相談ができる点もうれしいポイントです。
大手銀行は安全性と信頼性に優れていますが、手数料やサービスの利便性ではネット証券に劣る部分があります。
ネット証券
手数料の安さやサービスの利便性を重視する方に適しています。ネット証券には、SBI証券や楽天証券などがあります。
ネット証券のデメリットとして、大手銀行のように対面で直接相談ができない点が挙げられます。
地方銀行
地方銀行は、地域密着型のサービスを求める方に適しています。地方銀行は、現在お住まい地域にある主要な銀行が該当します。
地方銀行は地域に根差したサービスを提供しますが、商品の種類やサービスの範囲が限られていることがあります。
新NISA口座を開設する際には、取り扱い商品、手数料、サービス内容、信頼度などを比較検討して選ぶようにしましょう。
特に、取り扱い商品には注意したいところです。例えば、新NISAを利用して個別株投資を考えている場合、証券会社しか取り扱っていません。
口座を開設する際には、自分に合った金融機関を選ぶことが重要になります。
新NISAにおすすめの証券会社は?
新NISAの口座開設ができるおすすめの証券会社は、
- SBI証券証券
- 楽天証券
- 松井証券
- マネックス証券
- auカブコム証券
の5社になります。
これらの証券会社は、いずれも取引手数料が無料となっています。しかし、サービス内容は、各社それぞれ異なっています。
例えば、SBI証券は取扱銘柄数とIPO銘柄の取り扱い数がNo.1。楽天証券は、楽天ポイントが貯まるサービスを展開しています。
各社のサービス内容については、新NISAの個別株取引手数料いくら?無料の証券会社と比較内容まとめでご紹介していますので、詳しくはそちらの記事をご覧ください。
新NISA口座の開設にあたっては、個々の投資スタイルやニーズに合わせて、最適な証券会社を選ぶことが重要です。
新NISAで毎年360万円を5年間投資する計画についてよくある質問

最後に、新NISAで毎年360万円を5年間投資する計画についてよくある質問をまとめました。
Q.新NISAの360万円枠とは何ですか?
新NISAは、非課税で投資ができる日本の制度です。この制度では、成長投資枠とつみたて投資枠を併用することで、年間最大360万円、5年間で合計1800万円まで非課税で投資することができます。
360万円枠とは、成長投資枠とつみたて投資枠を併用したときの年間投資枠を意味しています。
Q.新NISAでの投資にはどのようなリスクがありますか?
投資には常にリスクが伴います。その中でも価格変動のリスクが最も多く、投資した商品の価格が下がってしまうと損失を被る可能性があります。
また、市場の変動や経済情勢の変化によってはリスクが高くなるため、初心者は過剰なリスクを取らないように注意する必要があります。
Q.新NISAで投資初心者におすすめの投資方法はありますか?
初心者は、最初から複数の銘柄に分散投資されている投資信託がおすすめです。分散投資とは、リスクを減らすために異なる企業や産業の株式に投資をしたり、異なる商品に投資をする方法です。
投資信託の中でも、低コストのインデックスファンドが初心者に適しています。リスクを抑えつつ、長期的な視点で投資を続けることが重要です。
新NISAで360万円を5年間投資する方法についてのまとめ
新NISAで毎年360万円を5年間投資するためには、360万円の投資計画と5年間の投資戦略が必要です。
360万円の投資計画では、毎月の投資額、分散投資、リスク管理についての計画を立てます。5年間の投資戦略では、長期的な視点、市場動向の分析、そして定期的なポートフォリオの見直しが必要になります。
また、投資で成功するためには、適切な商品選びが大切です。よく調べて、自分に合った商品を選びましょう。