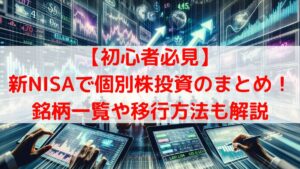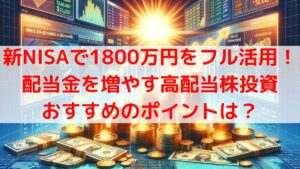2024年1月から始まった新NISAで1800万円を積立投資した場合、資産額と運用益はいくらになるのでしょうか?
今回は、新NISAで1800万円を積立投資したときの10年後と20年後のシミュレーション結果についてや、積立投資に最適な個別株や投資信託について詳しく解説します。また、新NISAの仕組み、非課税枠の活用方法、そして「ほったらかし運用」のメリットについても解説します。
この記事を読めば、新NISAでの積立投資の始め方、おすすめの投資商品の選び方などが学べ、長期的な資産形成に役立てることができます。新NISAを最大限に活用し、効率的に資産を増やしていくための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
新NISAの仕組みについて
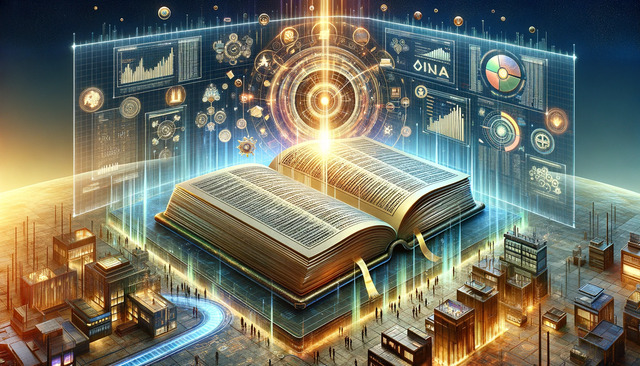
新NISAの導入により、投資家は成長投資枠とつみたて投資枠を活用して、自分の投資スタイルに合わせた資産形成を行うことができるようになりました。
さらに新NISAの魅力は、非課税期間が無期限であることや、売却した分の非課税枠が翌年に復活することです。
そこで、新NISAの仕組みについて解説します。
成長投資枠とつみたて投資枠
新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠があり、自分の投資のスタイルに合わせて使い分けることができます。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 投資対象商品 | 上場株式 投資信託 ETF(上場投資信託) REIT(不動産投資信託) | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
成長投資枠では、年間240万円まで投資することができ、上場株式や投資信託など、幅広い商品に投資することができます。この投資枠を使うことにより、例えば、成長が期待できる企業の株式に投資をして、大きなリターンを狙うことができます。
一方、つみたて投資枠は年間120万円までの投資が可能で、長期の積立投資に適した投資信託に投資することができます。この投資枠を使うことにより、リスクを抑えながら資産形成を目指すことができます。
投資家は、成長投資枠とつみたて投資枠をうまく活用することによって、効率的に資産形成を実現することができます。
非課税期間が無期限
新NISAの最大の魅力は、非課税期間が無期限であることです。つまり、投資で得た利益に対して、一生税金がかかりません。
旧NISAでは非課税期間に制限があり、最大でも20年間まででした。しかし、新NISAではこの非課税期間が無期限であるため、長期にわたって非課税で資産形成が可能になります。
例えば、20歳から投資を始めて60歳まで運用した場合、旧NISAだと非課税期間が途中で終了します。そのため、資産を売却するか、課税されながら運用を続けるしかありませんでした。
しかし、新NISAなら非課税期間が無期限であるため、税金を気にすることなく、長期的な資産形成を実現することができます。
売却した分の非課税枠が翌年に復活
新NISAでは、売却した分の非課税枠が翌年に復活します。そのため、投資家は投資戦略に応じて、非課税枠を最大限に活用することができます。
例えば、非課税枠上限まで使い切ったとき、含み益が大きい資産を売却することによって、その分の非課税枠が翌年に復活し、次の投資のチャンスに備えることができます。
新NISAでは売却した分の非課税枠が翌年に復活するため、柔軟性の高い資産運用ができ、長期的な資産形成をサポートします。
新NISAの非課税枠の活用方法について

新NISA制度は、投資によって得られた利益に対して、税金がかからないというメリットがあります。この制度を上手く活用することによって、長期的な資産形成を実現することができます。
ここでは、新NISAの非課税枠の活用方法について、具体的に解説していきます。
非課税枠は1800万円
新NISAの非課税枠1800万円を最大限活用するためには、計画的な投資戦略が必要です。
例えば、成長性の高い個別株や、安定した収益が見込める投資信託に投資をすることによって、リスクとリターンのバランスが良いポートフォリオを構築することができます。。
計画的に投資を行うことによって、非課税枠1800万円を最大限に活用することができます。
年間投資枠は最大360万円
新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠を併用することで、年間最大360万円まで非課税で投資することができます。2つの投資枠をうまく活用することで、リスク分散と資産形成を同時に実現することができます。
例えば、成長性の高い個別株と、安定したリターンが狙える投資信託をバランスよく組み合わせることで、リスクを分散しながら長期的な資産形成実現することができます。
成長投資枠とつみたて投資枠を併用し、年間投資枠を最大360万円まで活用することによって、より多くの資金を非課税で投資することができます。
非課税枠は再利用する
新NISA制度では、含み益が大きくなった資産や、損失が出ている資産を売却すると、その非課税枠を再利用することができます。これによって、ポートフォリオの調整を行いながら、再び非課税枠を利用することができます。
例えば、大きく値上がりした資産を売却し、その資金で再投資することによって、非課税枠を再利用しながら資産形成を加速させることができます。また、損失を出している資産を売却することによって、非課税枠を再利用しながらよりリターンが期待できる商品へ資金をシフトし、ポートフォリオの健全化を図ることができます。
新NISAを活用し、長期的な資産形成を目指しましょう。
新NISAにおすすめのほったらかし運用

新NISA制度を利用する際、おすすめの方法が「ほったらかし運用」です。この方法は、時間や労力をあまりかけずに、資産運用ができる効率的な運用方法です。
そこで、ほったらかし運用のメリットについて解説します。
時間をかけずに投資できる
ほったらかし運用の最大のメリットは、市場の動きに一喜一憂することなく、時間をかけずに投資を続けることができる点です。
また、この運用方法は、忙しい人や投資に多くの時間を割けない人でも、効率的に資産を増やすことができます。
例えば、目標とする金額まで積立投資した後にほったらかし運用を続けることにより、市場の動きに一喜一憂することなく、長期的な視点で資産を増やすことができます。
感情に左右されずに投資を続けられる
ほったらかし運用は、頻繁に売買を行うことなく、長期的な視点で投資を行う方法です。そのため、市場の短期的な値動きに一喜一憂することなく、冷静になって投資を続けることができます。
市場の値動きに対して一喜一憂してしまうと、感情的になってしまい、結果的に失敗のリスクが高まります。しかし、長期的な視点でほったらかし運用を続けることで、市場の値動きに左右されず、長期的に資産を増やすことができます。
長期的に資産形成を目指すことができる
新NISAを活用したほったらかし運用は、長期投資によって資産を形成することができます。
市場は短期間で大きく動くことがありますが、長期的には経済の成長と共に資産価値も上昇していきます。さらに、新NISAでは利益に対して非課税となるため、ほったらかし運用との相性も抜群です。
例えば、グローバル企業に投資するインデックスファンドを購入し、あとは10年以上ほったらかし運用を続けることで、経済の成長に伴って資産価値も上昇してきます。
新NISAのほったらかし運用は、初心者でも取り組みやすく、長期的に安定した資産形成を目指すことができる運用方法です。
新NISAで1800万円を積立投資後にほったらかし運用!シミュレーション結果は?

新NISA制度を利用して積立投資を行い、その後はほったらかしで運用したときのシミュレーション結果を見ていきましょう。
ここでは、年率5%で積立投資を行い、その後はほったらかし運用によって10年後、20年後に運用益や資産額がどのくらいになるのかを見ていきます。
積立投資後にほったらかし運用!10年で資産額と運用益はいくら?
年率5%で積立投資を行い、その後ほったらかし運用したときの10年後の運用益と資産額は次の通りになります。
単位:万円
| 年間360万円を 5年間積立投資 | 年間180万円を 10年間積立投資 | 年間120万円を 15年間積立投資 | |
|---|---|---|---|
| 投資金額(元本) | 1800 | 1800 | 1200 |
| 運用益 | 868 | 577 | 385 |
| 資産額 | 2668 | 2377 | 1585 |
積立投資後にほったらかし運用したときの10年後のシミュレーション結果は、新NISAで1800万円をフル活用!10年後の運用シミュレーションは?でご紹介していますので、詳しくはそちらで確認して下さい。
積立投資後にほったらかし運用!20年で資産額と運用益はいくら?
年率5%で積立投資を行い、その後ほったらかし運用したときの20年後の運用益と資産額は次の通りになります。
単位:万円
| 年間360万円を 5年間積立投資 | 年間180万円を 10年間積立投資 | 年間120万円を 15年間積立投資 | 年間90万円を 20年間積立投資 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資金額(元本) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 運用益 | 2542 | 2072 | 1670 | 1325 |
| 資産額 | 4342 | 3872 | 3470 | 312 |
積立投資後にほったらかし運用したときの20年後のシミュレーション結果は、新NISA非課税枠1800万円完全活用!20年後のシミュレーション結果は?でご紹介していますので、詳しくはそちらで確認して下さい。
新NISAの積立投資におすすめの商品

新NISA制度を利用して積立投資を行う場合、どのような商品を選ぶべきかは投資初心者にとって重要な悩みです。
ここでは、積立投資におすすめの個別株と投資信託について、選び方と具体的な商品例を紹介します。
積立投資におすすめの個別株
積立投資で個別株を選ぶ際には、長期的な視点で安定した成長が見込める企業や、配当利回りが高い企業を選ぶことが重要です。
長期的な成長が見込まれる企業は、長期投資によって株価が上昇していきます。
安定した成長が見込まれる個別株には、
- トヨタ自動車
- ソニー
- 任天堂
- NTT
- 三菱UFJ銀行
などが挙げられます。
配当利回りが高い企業は、株価の変動に関わらず定期的な配当金収入があります。
配当利回りが高い個別株には、
- JT
- 住友商事
- 丸紅
- 三菱商事
- キャノン
などが挙げられます。
積立投資におすすめの投資信託
積立投資において、複数の銘柄に分散投資されたインデックスファンドは、長期的な資産形成に適しています。
インデックスファンドは、特定の指数に連動するように運用されるため、市場全体の平均的なリターンが狙えます。また、アクティブファンドに比べて運用コストが低いというメリットがあります。
おすすめのインデックスファンドには、
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 楽天・全米株式インデックスファンド
- ニッセイ 日経225インデックスファンド
などが挙げられます。
新NISAで口座を開設する方法

新NISA制度を利用して投資を始めるには、まず口座を開設する必要があります。また、どの金融機関で口座を開設するかも重要になります。
そこで、新NISAの口座開設の手順と金融機関を選ぶポイントについて解説します。
新NISA口座の開設手順
新NISA口座を開設する手順は、一般的に以下のようになります。
新NISA口座を開設する金融機関を選びます。
運転免許証やマイナンバーカードなど、口座開設に必要な書類を準備します。
各金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
必要書類をそろえ、金融機関のホームページや店頭窓口で口座開設の申し込みを行います。
ホームページで口座開設の申し込みを行う場合、必要書類はデジタルで提出できる場合が多く、非常に便利です。
申し込み後、書類の審査が行われます。新NISAの口座開設には税務署の審査も含まれるため、通常1~2週間程度かかります。
金融機関から口座開設の承認が下りれば、投資を始めることができます。
新NISAの口座開設には、ネット証券、大手銀行、信託銀行などがあります。サービス内容はそれぞれ異なりますので、自分に合った金融機関を選びましょう。
金融機関の選び方について
新NISA口座を開設する金融機関を選ぶ際には、取り扱い商品の種類、手数料、サービスの質などを比較検討することが重要です。
取り扱い商品の種類
各金融機関によって、取り扱い商品の種類が異なります。自分が投資したい商品を取り扱っているのか、事前に確認しておきましょう。
手数料
取引手数料や口座維持費用など、新NISA口座にはさまざまな手数料がかかります。
サービスの質
投資初心者の場合、投資に関する相談やサポート体制が充実している金融機関が良いかもしれません。
利便性
オンラインでの取引がスムーズに行えるか、アクセスしやすい場所に窓口があるかなど、日常的に利用する上での利便性も重要になります。
例えば、ネット証券の場合は手数料が低く、オンラインで手軽に取引することができます。また、個別株を取り扱っているのは、証券会社のみとなっています。
大手銀行の場合は手数料が高い傾向にありますが、投資の悩みについて専門家に直接相談することができます。
新NISA口座を開設する際には、自分の投資スタイルやニーズに合った金融機関を選ぶことが大切です。手数料やサービス内容などをしっかりと比較検討し、自分に合った金融機関を選びましょう。
新NISAで投資商品を購入する方法

新NISAで投資商品を購入することは、将来の資産形成に向けた大切な第一歩となります。
ここでは、新NISAで投資商品を購入する際の具体的な方法と、選ぶポイントについて解説します。
新NISA口座で投資商品を購入する手順
新NISA口座で投資商品を購入する手順は、以下のように進めます。
新NISAでは、個別株、投資信託、ETF、REITが購入できます。また、取り扱い商品の種類は、金融機関によって異なります。
購入する商品が決まったら、注文を出します。
注文方法には、指値注文(希望する価格で注文)と成行注文(現在の市場価格で注文)があります。
注文が完了すると、市場で取引が行われます。取引が成立すると、商品の購入は完了です。
投資商品を選ぶ際には、投資目的、リスク許容度、投資期間などを明確にし、慎重に選ぶようにしましょう。
また、投資信託を選ぶ際には、信託報酬などのコストもチェックするようにしましょう。
新NISA口座で投資商品を選ぶポイント
新NISA口座で投資商品を選ぶ際には、
- 投資目的
- リスク許容度
- 投資期間
を明確にすることが重要です。
自分の投資目的に合った投資商品を選ぶことで、長期的な資産形成を実現することができます。
投資商品には個別株、投資信託、ETFなどがあり、それぞれの商品にはリスクとリターンが異なります。自分のリスク許容度や投資期間に見合う商品を選ぶことで、無理なく投資を続けることができます。
例えば、リスク許容度が高くて高いリターンを求める場合、成長性がある個別株が適切といえます。一方、リスク許容度が低く、長期的に安定したリターンを求める場合には、インデックスファンドなどの投資信託が適切といえます。
新NISAの1800万円枠についてよくある質問

最後に、新NISAの1800万円枠についてよくある質問をまとめました。
Q.新NISAの1800万円枠とは何ですか?
新NISAの1800万円枠とは、最大1800万円まで非課税(所得税や住民税がかからない)で投資することができる枠のことを指します。
これは、旧NISAに比べて投資枠が大幅に拡大されました。
Q.新NISAの1800万円枠を利用するメリットは何ですか?
新NISAの1800万円枠を利用するメリットは、大きく二つあります。
一つ目は、投資による利益(売却益や配当金収入による利益)に対して、税金がかからない点です。
二つ目は、投資の機会を広げることができる点です。特に資産形成を目指す投資家にとっては、チャンスとなります。
Q.株式投資初心者が新NISAの1800万円枠を利用する際の注意点は?
株式投資初心者が新NISAの1800万円枠を利用する場合、いくつかの注意点があります。
投資にはリスクが伴うため、自分のリスク許容度となる範囲内で行うことが大切です。また、自分でしっかりと投資先の企業についてリサーチを行うことも必要です。
さらに、長期的な視点で投資を続けることが重要になります。
新NISAで1800万円積立投資した場合のシミュレーション結果のまとめ
新NISA制度を利用して年率5%で1800万円を積立投資し、その後ほったらかしで運用した場合のシミュレーション結果は、次の通りです。
10年後の結果
- 年間360万円を5年間積立投資した場合:運用益は868万円、資産額は2668万円
- 年間180万円を10年間積立投資した場合:運用益は577万円、資産額は2377万円
- 年間120万円を15年間積立投資した場合:運用益は385万円、資産額は1585万円
20年後の結果
- 年間360万円を5年間積立投資した場合:運用益は2542万円、資産額は4342万円
- 年間180万円を10年間積立投資した場合:運用益は2072万円、資産額は3872万円
- 年間120万円を15年間積立投資した場合:運用益は1670万円、資産額は3470万円
- 年間90万円を20年間積立投資した場合:運用益は1325万円、資産額は3125万円
シミュレーション結果から、運用期間が長いほど、また積立額が多いほど、運用益と資産額が大きくなることが分かります。