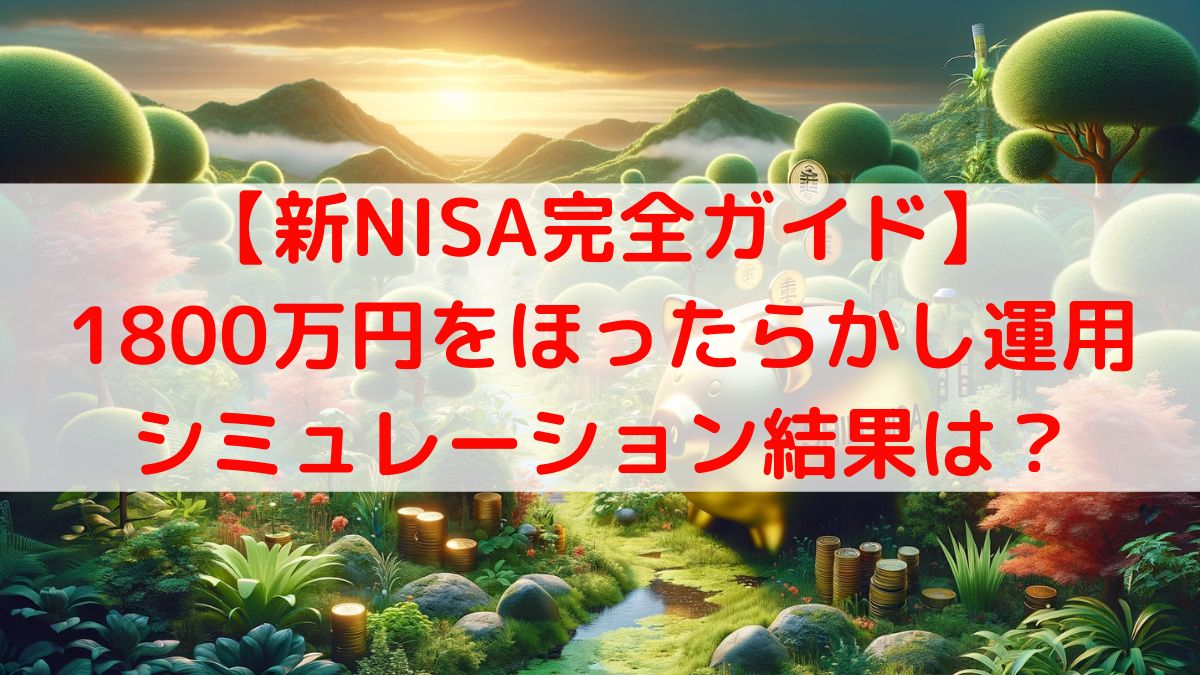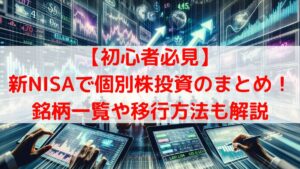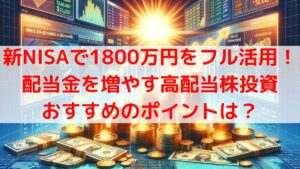新NISAの導入により、多くの投資家が非課税枠1800万円をフル活用するための投資計画を立てています。では、この非課税枠を使い切った後、ほったらかし運用でも資産は増えていくのでしょうか?
今回は、新NISAを使い切った後のほったらかし運用によるメリットとデメリット、さらには10年後と20年後の資産額のシミュレーション結果について詳しく解説します。また、非課税枠を使い切るための具体的な投資計画についても紹介します。
この記事を読めば、将来の資産形成に向けたステップを理解することができ、ほったらかし運用でも効果的に資産を増やす方法を学ぶことができますので、最後までご覧ください。
新NISAの概要について
2024年から始まった新NISAは、旧NISAの制約を緩和し、投資家の長期的な資産形成をサポートする制度です。
そこで、新NISAの概要について詳しくご紹介します。
新NISAとは?
新NISAは、2024年から始まった新しい少額投資非課税制度です。
この制度は旧NISAの制約を緩和し、投資家の長期的な資産形成をサポートすることが目的です。
例えば、旧NISAでは年間投資枠が最大120万円まででしたが、新NISAでは最大360万円に拡大されました。また、保有する資産を売却すれば、翌年からその分の非課税枠を再利用することができるようになりました。
新NISAの非課税枠と非課税期間
新NISAでは、非課税枠と非課税期間も拡大されました。
具体的に説明すると、旧NISAの非課税枠は最大800万円まででしたが、旧NISAでは最大1800万円まで拡大。非課税期間も無期限となりました。
新NISAでは、非課税枠と非課税期間の拡大によって、投資家の長期的な資産形成をサポートします。
新NISAの非課税枠1800万円を使い切るための投資計画
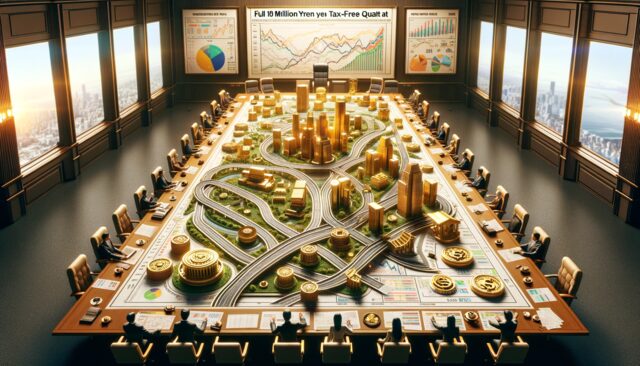
新NISAの非課税枠1800万円を使い切るためには、長期的な視点で計画を立てる必要があります。
1800万円をフル活用する投資計画の立て方は、
という手順で計画を立てていきます。
それでは、それぞれの投資計画の立て方について具体的に解説していきます。
手順1.投資期間を決める
最初に、非課税枠1800万円をフル活用するためには、投資期間を決めます。
どのくらいの投資期間にするのか、それによって投資方法や商品選びが変わってきます。
投資期間は、
短期投資(1年~5年)
リスクを取って、短期的な利益を目指す。
中期投資(5年~10年)
リスクとリターンのバランスを重視する。
長期投資(10年以上)
リスクを抑えながら、長期的な資産形成を目指す。
という風に決めます。
投資期間が10年以上と長ければ、市場の短期的な動きに対してリスクを抑えることができるため、長期的な資産形成を目指すことができます。
一方、投資期間が短くなれば市場の動きに対してリスクが高くなるため、短期的に利益を目指さなければいけません。
自身のリスク許容度に合わせて、投資期間を決めましょう。
手順2.投資目標を設定する
次に、投資目標を設定しましょう。投資目標によって、必要とする金額が変わってきます。
投資目標の設定には、
老後資金
必要資金を算出し、目標金額を設定する。
教育資金
子どもの進学費用を算出し、目標金額を設定する。
セカンドライフ資金
理想のセカンドライフに必要な資金を算出し、目標金額を設定する。
といったことが挙げられます。
例えば、将来の老後資金のために投資を行う場合、目標金額は2000万円必要かもしれません。また、子どもの教育資金のために投資を行う場合、目標金額は1000万円必要かもしれません。
それぞれの投資目標に合わせて、目標金額を設定しましょう。
手順3.積立投資と一括投資のどちらを選択する
次に、積立投資と一括投資のどちらかの投資方法を決めます。どちらを選択するかは、個人の状況によって異なります。
積立投資では、毎月一定額を投資します。この投資方法は、少額から始めることができ、長期的にはドル・コスト平均法によって商品の購入単価を下げることができます。
一括投資の場合、一度にまとまった金額を投資します。もし投資のタイミングが良ければ、商品の値上がりによって短期間で大きな利益を獲得する可能性があります。
積立投資は長期的な視点での投資方法になり、一括投資は短期的な視点での投資方法になります。どちらの方法を選ぶのかは、投資家の投資期間やリスク許容度を考慮しながら決定する必要があります。
手順4.毎月の投資金額を決める
投資期間や投資目標に基づいて、毎月の投資金額を決めます。
投資金額は、家計の収支を把握し、無理のない範囲で決めるようにします。もし、毎月の収入だけで目標達成が難しい場合は、ボーナスなどの臨時収入のときにまとめて投資しましょう。
手順5.投資商品を選ぶ
新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠を利用することができます。
成長投資枠では、個別株やアクティブ型の投資信託など、リスクとリターンが高い商品に投資することができます。
つみたて投資枠では、インデックスファンドなど、長期投資に適した安定性のある商品に投資することができます。
成長投資枠とつみたて投資枠をバランスよく活用し、自身の投資期間やリスク許容度に基づき、分散投資を心がけながら投資商品を選びましょう。
手順6.定期的にポートフォリオを見直す
投資を始めたら、定期的に見直してポートフォリオの調整を行います。
資産の運用状況や、目標金額の達成状況、経済状況やライフタイルの変化に合わせ、投資計画を修正していきます。
もし、投資計画と資産状況にズレが生じてしまった場合は、ポートフォリオのリバランスで調整を行うようにしましょう。
新NISAのほったらかし運用のメリットとデメリット
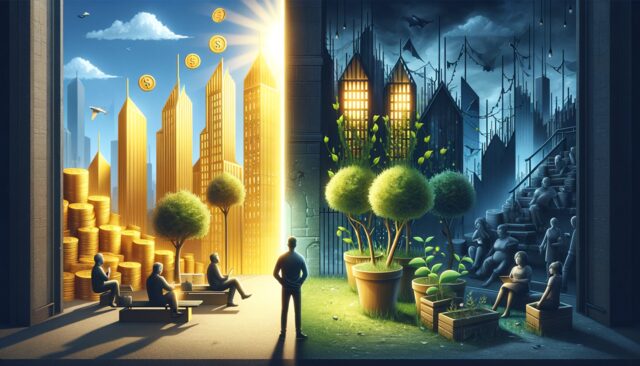
新NISAの最大1800万円の非課税枠を使い切った後のほったらかし運用は、忙しい方や投資に時間を割けない方にとっては有効となる運用方法です。
しかしその一方で、デメリットも存在します。
そこで、ほったらかし運用のメリットとデメリットについて解説します。
ほったらかし運用のメリット
新NISAの非課税枠をフルに活用した後、ほったらかしにして運用する方法は、特に忙しい方や投資に多くの時間を割けない方にとって有効な運用方法です。そのうえ手間がかからず、長期投資によって資産形成を行うことができます。
例えば、世界の経済成長に連動するようなグローバルインデックスファンドに投資をすれば、各国の経済成長に伴って資産額を増やすことができます。
その他にも、頻繁に売買を行わないのでコストを抑えることができたり、市場の短期的な変動に惑わされないというメリットがあります。
ほったらかし運用のデメリット
一方、ほったらかし運用のデメリットは、定期的な利益確定ができない点です。
例えば、保有する個別株が画期的な商品を発売し、思わぬ好材料に市場が反応して株価が一時的に上昇した場合でも、利益確定のチャンスを逃してしまう可能性があります。
このようなチャンスを逃さないためにも、ほったらかし運用を行う際には定期的に市場のニュースや企業情報をチェックし、ポートフォリオに影響を与える重要な情報に対応して、機会損失を防ぎましょう。
新NISAの非課税枠1800万円使用後のほったらかし運用で資産額はいくら?

新NISAの非課税枠1800万円を使い切った後、ほったらかし運用は時間と手間をかけずに資産形成を目指すことができます。
ほったらかし運用で10年後や20年後の資産額はいくらになるのでしょうか?そこで、非課税枠1800万円を使い切った後の資産額についてシミュレーションでご紹介します。
ほったらかし運用で10年後の資産額をシミュレーション
新NISAの非課税枠1800万円を5年から15年で使い切り、年率5%でほったらかし運用したときの10年後の資産額は次の通りになります。
単位:万円
| 1800万円を5年で 使い切る場合 | 1800万円を10年で 使い切る場合 | 1800万円を15年で 使い切る場合 | |
|---|---|---|---|
| 投資金額 (元本) | 1800 | 1800 | 1200 |
| 運用益 | 868 | 577 | 385 |
| 資産額 | 2668 | 2377 | 1585 |
新NISAの非課税枠1800万円を使い切り、ほったらかし運用したときの10年後の運用シミュレーション結果は、新NISAで1800万円をフル活用!10年後の運用シミュレーションは?でご紹介していますので、詳しくはそちらで確認して下さい。
ほったらかし運用で20年後の資産額をシミュレーション
新NISAの非課税枠1800万円を5年から20年で使い切り、年率5%でほったらかし運用したときの20年後の資産額は次の通りになります。
単位:万円
| 1800万円を5年で 使い切る場合 | 1800万円を10年で 使い切る場合 | 1800万円を15年で 使い切る場合 | 1800万円を20年で 使い切る場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 投資金額 (元本) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 運用益 | 2542 | 2072 | 1670 | 1325 |
| 資産額 | 4342 | 3872 | 3470 | 3125 |
新NISAの非課税枠1800万円を使い切り、ほったらかし運用したときの20年後の運用シミュレーション結果は、新NISA非課税枠1800万円完全活用!20年後のシミュレーション結果は?でご紹介していますので、詳しくはそちらで確認して下さい。
新NISAでほったらかし運用するなら投資信託がおすすめ
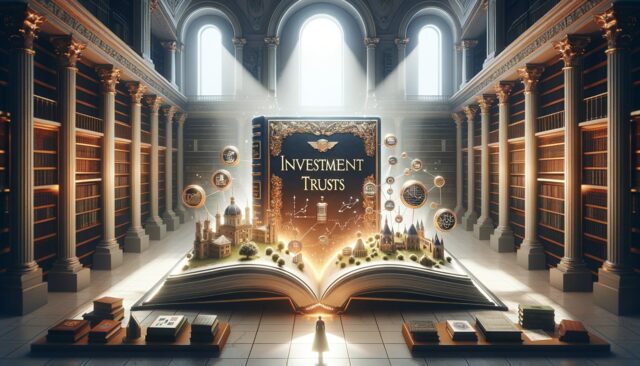
新NISA制度を活用して、手間をかけずに資産を増やしたい方は、投資信託がおすすめです。
投資信託はプロのファンドマネージャーが資産運用を代行し、個人投資家に代わって市場の機会を捉え、リスクを管理します。
また投資信託を選べば、忙しい方や投資に多くの時間を割けない方でも、ほったらかしで多様な資産に分散投資することが可能になります。
投資信託を選ぶメリットには、
時間と手間がかからない
投資信託はプロのファンドマネージャーによって運用されているので、自分で商品を選ぶ必要がなく、時間と手間がかかりません。
長期的な資産形成に適している
投資信託は長期的な視点で運用することで、複利効果によって資産を増やすことができます。
個別株よりもリスクが低い
投資信託は複数の企業に分散投資しているので、個別株よりもリスクが低くなります。
などが挙げられます
例えば、投資信託の中には、日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動するファンドがあります。そのような投資信託を選ぶことで、市場の平均リターンを享受しつつ、プロのファンドマネージャーがあなたに代わって資産運用を行ってくれます。
投資信託を利用すれば、忙しい方や投資に多くの時間を割けない方でも、ほったらかしで資産運用を行うことができます。これにより、新NISAの非課税枠を効果的に活用しながら、長期的な資産形成を目指すことが可能となります。
新NISAで口座開設ができる金融機関の選び方
新NISAを始めるためには、金融機関で専用の口座を開設する必要があります。
金融機関にはそれぞれ特徴がありますので、各社比較検討した上で自分の投資スタイルに合った金融機関を選ぶことが重要です。
例えば、手数料の安さを重視するなら、オンラインの証券会社が適しているでしょう。もし専門家によるサポートを直接受けたいなら、大手証券会社が適しているでしょう。
オンライン証券は、低コストで自分で投資判断を下すことができる投資家に適しています。それとは対照的に、大手証券会社は、投資相談や資産管理のアドバイスなど、より手厚いサポートを受けることができます。
自分の投資目的やスタイルに合った金融機関を選ぶことが、投資で成功する第一歩となります。
新NISAのほったらかし運用についてよくある質問

最後に、新NISAのほったらかし運用についてよくある質問をまとめました。
Q.ほったらかし運用とはどのような投資方法ですか?
ほったらかし運用とは、日々の値動きに一喜一憂せず、長期間そのままにしておく運用方法です。
定期的なリバランスや配当の再投資を行うことはありますが、基本的には積極的な売買を行わず、市場の成長に任せる運用スタイルです。
Q.ほったらかし運用のメリットとデメリットは何ですか?
メリットとしては、長期投資で資産を増やすことができ、投資の専門知識が少なくても運用できる点があります。また、日々の市場動向に一喜一憂する必要がなく、精神的な負担が少なくなります。
デメリットとして、個別株などの急激な値上がりに対する利益確定のチャンスを逃してしまうことが挙げられます。
Q.新NISAを使う際の注意点は何ですか?
新NISAを使う際の注意点としては、まず非課税枠を超えて投資をしないことが大切です。また、商品選定は慎重に行い、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことが重要です。
さらに、長期投資を心掛け、市場の短期的な変動に惑わされないことも大切です。定期的なポートフォリオの見直しを行い、必要に応じて調整を行いましょう。
新NISAで1800万円ほったらかし運用のシミュレーション結果についてのまとめ
新NISAの非課税枠1800万円をほったらかし運用したときのシミュレーション結果は、次の通りになります。
10年後のほったらかし運用のシミュレーション結果
1800万円を5年で使い切る場合:資産額は約2668万円(運用益868万円)
1800万円を10年で使い切る場合:資産額は約2377万円(運用益577万円)
1800万円を15年で使い切る場合:資産額は約1585万円(運用益385万円)
20年後のほったらかし運用のシミュレーション結果
1800万円を5年で使い切る場合:資産額は約4342万円(運用益2542万円)
1800万円を10年で使い切る場合:資産額は約3872万円(運用益2072万円)
1800万円を15年で使い切る場合:資産額は約3470万円(運用益1670万円)
1800万円を20年で使い切る場合:資産額は約3125万円(運用益1325万円)
この結果は年率5%の運用を前提にしていますが、運用期間が長いほど、元本に対する運用益が大きくなることが見て取れます。